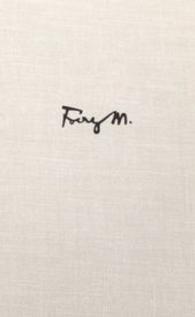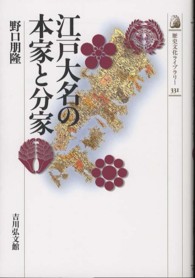- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
職場にはパワハラ、モラハラ、セクハラなど数々の嫌がらせ行為があり、多くの被害者を生み続けている。しかし日本では、社会的なルール不足により被害者の救済もままならず、基本的な統計も整っていないため実態把握すら難しい。ハラスメント規制の先進地域であるEU諸国の法整備に通じ、民間団体で相談活動に関わる著者が、日本での概況を解説。参考となる判例や法律の根拠、海外での事例などを紹介し、対策を提言する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かごむし
25
2年前の本。働き方改革とか浸透してきたし、読む前は時代遅れの本かなと思った。とんでもない。いじめは個人の資質やコミュニケーションの問題で片付けられていたものが、組織の構造的な問題として認識され、ハラスメントの概念へと進化した。だが、日本の場合、ハラスメントという包括的な概念よりも、セクハラ・パワハラ・マタハラなど、マスコミ受けする細分化された概念が歩き回ってしまった。細分化された言葉にあてはまらないことで、本来「人格や尊厳の侵害」というハラスメント概念で救済すべき人や事象が見えなくなることが問題と知る。2020/04/28
もえたく
17
財務省事務次官の件もあり、タイムリーな新書。著者曰く、日本では社会的なルール不足により被害者の救済もままならず、基本的な統計も整っていないため実態把握も難しいそうです。日本での実例と、海外の法整備状況を紹介し、被害者と企業のための「ハラスメント対策10カ条」を提言されてます。パワハラという用語が国際的には通用しない「素性の良い英語」ではないと厚生労働省の専門検討会で論難されていたが、結局、マスコミが使用しているのでと国が公認したとのこと。色々と勉強になりました。2018/04/21
香菜子(かなこ・Kanako)
13
職場のハラスメント、なぜ起こり、どう対処すべきか。大和田敢太先生の著書。職場でのハラスメント、パワハラ、セクハラ、モラハラを防ぐには、全員がパワハラ、セクハラ、モラハラに対する知識や理解を高めることが一番の近道。パワハラ、セクハラ、モラハラについての研修を義務付けることが大切だと思う。2018/06/16
香菜子(かなこ・Kanako)
11
職場のハラスメント、なぜ起こり、どう対処すべきか。大和田敢太先生の著書。職場でのハラスメント、パワハラ、セクハラ、モラハラを防ぐには、全員がパワハラ、セクハラ、モラハラに対する知識や理解を高めることが一番の近道。パワハラ、セクハラ、モラハラについての研修を義務付けることが大切だと思う。2018/06/16
sk
9
この問題について体系だって書かれた良書。ハラスメントは社会的問題であり構造的問題であることを解説。2018/11/07
-

- 電子書籍
- HEROLL-ヒーロール-(3) GA…
-
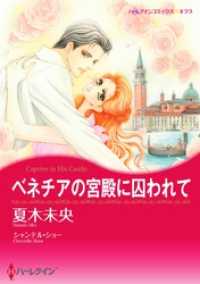
- 電子書籍
- ベネチアの宮殿に囚われて【分冊】 7巻…