内容説明
プロならではのREC&MIXの奥義が、いま明かされる!
現役プロ・エンジニアが贈る、レコーディング&ミキシングに関する詳細な解説書。第1章では現場で使用する機材について紹介し、続く第2章でレコーディングのノウハウを、第3章でミキシングのノウハウを、具体例を交えて大公開! 分かりやすく、語りかけるような口調で明かされるテクニックや知識の数々は、レコーディング・エンジニア志望者のみならず、自宅録音系ミュージシャン、DTMerにもマストな、とても貴重なものとなっています。DAW全盛の今こそ押さえておきたい、“全知識”なのです。
*この電子書籍は固定レイアウト方式で作成されています。文字の拡大・縮小や、検索、ハイライトなどの機能は利用できません。
目次
■第1章 機材編
≪マイクロフォン≫
◎ダイナミック・マイク
◎コンデンサー・マイク
◎リボン・マイク
◎マイクの機能
◎実際のマイクの選び方
≪コンソール≫
◎スタジオでのシステム
◎コンソールの入力部
◎コンソールの出力部
◎コンソールのその他の機能
≪アウトボード≫
◎マイク・プリアンプ
◎イコライザー
◎ダイナミクス系
◎リバーブ
◎ディレイ
◎マルチエフェクターを経てプラグイン・エフェクトへ
◎自作のススメ
≪レコーダー≫
◎アナログMTR
◎デジタルMTR
◎マスター・レコーダー
≪DAW(Digital Audio Workstation)≫
◎DAWは仮想スタジオ
◎コンピューターについて
≪モニター・スピーカー≫
◎モニター・スピーカーは音の出口
◎ラージ・スピーカーとスモール・スピーカー
◎スモール・スピーカーのセッティング
◎モニターのボリューム
◎自宅スタジオでのセッティング
■第2章 レコーディング編
≪プロ・スタジオの特徴≫
◎さまざまなプロ・スタジオ
◎プロ・スタジオと自宅スタジオの違い
≪レコーディングの心得≫
◎レコーディングにおいて考慮するべき点
◎音が焦点を結ぶ場所にマイクを置く
◎エンジニアにとっての感受性とは?
≪ドラムの収録≫
◎マイク1本でのドラムの収録
◎2~3本のマイクでのドラムの収録
◎マルチマイクでのドラムの収録
≪ベースの収録≫
◎ベース・アンプのマイクによる収録
◎エレキベースのライン録音
◎ライン+マイクでのエレキベースの収録
◎ウッドベースの収録
◎コンプレッサーやイコライザーのかけ録り
≪ギターの収録≫
◎エレキギターへのマイキング
◎例外だらけのインダストリアル系
◎アコースティック・ギターへのマイキング
◎アコギにおけるかけ録り
≪ピアノの収録≫
◎マイク1本でのピアノ収録
◎複数のマイクでのピアノ収録
≪ストリングスの収録≫
◎スタジオでのストリングス録り
≪ボーカルの収録≫
◎ボーカル録りの注意点
◎ボーカルに適したマイクとマイク・プリアンプ
◎コンプレッサーのかけ録りが必要な場合
≪ラインものの収録≫
◎楽器を知ることが重要
◎ケーブルで音が変わる?
≪モニタリングについて≫
◎2ミックスでのモニタリング
◎プレイヤー用のモニター・ミックスが必要な場合
■第3章 ミキシング編
≪ミキシング概論≫
◎ラフ・ミックスと完成ミックス
◎ミックスの視覚イメージ
◎ミキシングの基本はボリューム操作
◎レベルについて
≪覚えておきたいテクニック≫
◎賢いコンプレッサーの使い方
◎賢いイコライザーの使い方
◎バス・ドラムとベースのつながり
◎ボーカルとオケをなじませる
◎楽器の定位を決める
◎音が細いミックスからの脱却
◎2ミックスの音圧を出す
≪編集テクニック≫
◎演奏ミスやノイズの補正
◎OKテイクの作り方
≪ミキシングの流れ≫
◎まずはスピーカーのセッティングから
◎実作業の第一歩は診断
◎アウトボードを使ったトリートメント
◎プラグインを使ったミキシング
◎打ち込みのストリングス
◎ボーカルの処理~完成
≪ミキシングの終わりに≫
◎最も重要なマスターの作成
■コラム
◎リファレンス・ディスク
◎エンジニアになるには
◎マスタリングについて
■APPENDIX
◎必聴ディスク・ガイド
◎ミニ用語集
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
たけ
ハンギ
zumisan
判家 悠久
-

- 電子書籍
- われら古細菌の末裔 微生物から見た生物…
-

- 電子書籍
- ZONE‐00 第18巻 あすかコミッ…
-
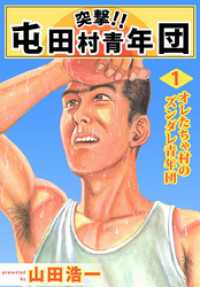
- 電子書籍
- 突撃!! 屯田村青年団(1) まんがフ…
-
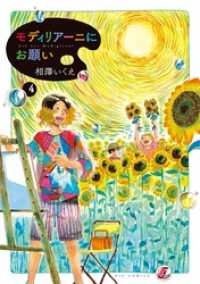
- 電子書籍
- モディリアーニにお願い(4) ビッグコ…
-
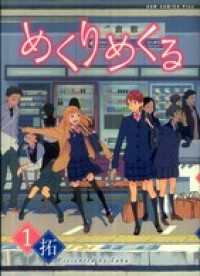
- 電子書籍
- めくりめくる 1巻 ガムコミックスプラス




