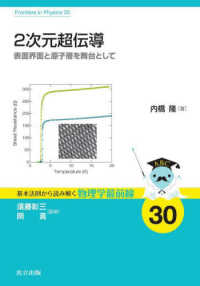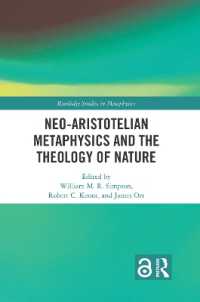内容説明
織田家中で最古参の重鎮・佐久間信盛は、本願寺攻めでの無為無策を理由に信長から突如追放された。一見理不尽な「リストラ」だが、婚姻や養子縁組による盤石の人脈を築けなかった結果とも言える。本書では、一万を超す大軍勢を任された柴田勝家・羽柴秀吉・滝川一益・明智光秀ら軍団長と、配下の武将たちの関係を、地縁・血縁などから詳細に検証。これまで知られなかった「派閥」の構造に迫り、各軍団の特性を明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
85
織田信長の家臣団における派閥と人間関係に焦点を当てた、職場やら社会での人間関係を知る人が読むと色んな意味で辛くなる本である。一例を上げれば家臣団や主家と姻戚関係を結ばなかったのが佐久間信盛の追放の原因となったとか、後ろ盾の無い羽柴秀吉が、主家から養子をもらい地位を安定させることに腐心していたとか、様々な人間模様が描かれている。明智光秀の謀反は織田家や譜代の与力が居ないからこそ成功したというのも、「しがらみの無い人間」の恐ろしさではなかろうかなどと思った。堺屋太一的戦国理解の浅はかさを思い知る好著である。2018/10/09
yamatoshiuruhashi
47
織田信長が地方の一家から天下を取るほどになったのか。その軌跡を彼の家臣たちの成り立ちから読み解いた本となっている。手にするまでは信長の一代記のようなものかと思っていたが、その家臣団の構成を逐一追って行くものだから、まるで創世記を読んでいる気分。それも聞き慣れない人物の名前が頻出するものだから筒井康隆の「バブリング創世記」の方を連想してしまった。どうせ俺は研究者じゃない、とわからない名前は通り過ぎれば概要はわかるが、著者に申し訳ない。2021/02/07
金吾
43
信長家臣団を詳細に調べてグルーピングをしています。明智軍団が、謀反を起こしやすい構造であったと言う話はなる程と思いました。2023/01/09
かごむし
37
織田信長誕生から本能寺の変までを、信長軍本体や方面軍を中心軸として、家臣団の地縁や血縁を丁寧に拾うことで、その関係性を浮かび上がらせている。歴史小説では端役や、そもそも出てこないような武将たちも重要人物として登場し、新たな視点を与えてくれる。とにかく読んでいて感じるのが、著者の情報収集に対する執念である。情報の精度に幅のある大量の資料を丹念に吟味しながら、1本1本の糸を紡ぐかのような記述は、それだけで感動する。戦国時代の小説を読んだ時に盛り上がる要素はこの本にはないが、興味深く最後まで読めた。面白かった。2017/11/21
Tomoichi
28
本書を読むと、信長の重臣や譜代・外様と多くの家臣が討死したり出奔したり追放されている。もちろん謀反で殺されたものもいる。何が言いたいかというと、そんな中で頭角を現した秀吉のことである。柴田勝家も合戦で何度も負傷しているし、討死にした重臣もいる。織田家などの近親の家系や譜代でも出世していない人達が無数にいるのです。卑賤の出と言われる秀吉は一体どう出世して行ったのか。本能寺の変後の立ち回りより、こっちの方が謎である。国衆などの力が強く信長も絶対君主ではない。秀吉の謎が深まるばかり。2022/05/28