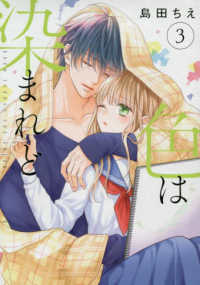- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
本が読まれなくなり、基本的な教養すら欠いた人間が世に溢れるようになった――こう嘆かれるようになって久しい。でも、本を読めば人は賢くなれるものだろうか。もちろん、否である。見栄でするやたらな読書は、人をどこまでも愚かにする。私たちには、文字に書かれたものを軽信してしまう致命的な傾向があるからだ。どうすれば、このような陥穽から逃れられるのか? ショーペンハウエル、アラン、仁斎、宣長など古今にわたる愛読の達人の営みに範をとり、現代人が本によって救われる唯一の道を示す。
目次
第一章 本とは何であったか/第二章 文字という〈道具〉を考える/第三章 生きる方法としての読書/第四章 愛読に生きよ/終わりの言葉
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
112
何でも読めばいいということではなく選んで読書をすべきだ、ということをご自分の読んだ本を紹介しつつ言われています。私などには耳の痛いことをいわれている気がします。「狐」こと山村修さんの本を思い出しました。私はまだまだそこまで達観できないのですが、もう少ししたらじっくり本を選んでいこう(300冊を選んでいるのですが)とは思っています。2018/10/12
佐島楓
68
ハウツー寄りの本かと思い手に取ったが、哲学を引きながらの文明批評だった。まあ「愛読の方法」はひとに教わるものではないが。2018/10/18
なかしー
47
今、私の読書の読み方、心のあり方、選び方についてこのままで良いのだろうか?と考えている途中だった時に軽い気持ちで手に取った。 本音を言うとタイトルより自己の読書経験から愛読書を選ぶ方法を説いた本ぐらいと高を括ってましたが、読了後は著者にはお見逸れ致していました、本当にすいませんと言う気持ちになった。 内容は古典から愛読書とは?愛読とは?読書とは?と考える本。 一度読んだだけではどうしても良書は本から来ると言う納得がいかない。2019/01/03
じろー
36
前半は読書論という趣きで比較的分かりやすく、共感もできる。後半のデカルトがどうの、伊藤仁斎がどうの、は難解でもあるし、興味もない。この後半部分はおそらく著者自身の「愛読」の産物である。ただ自分にとってはそんなものを見せられてもどうしようもない。大学の文学部の先生による読書論なのであまりに偏りがあるし、「愛読」を必要としている人がどれだけいるか疑問である。状況上、なにも「愛読」でなくても読んだ方が良い場合というのは無数にあると思う。著者の言っている事は良く分かるが、普通の読書を批判しすぎであると感じた。2019/05/18
ロマンチッカーnao
31
本は批判するために読むのではなく、多読し、読んだ気になるのは愚かな自分を作る。良書に出会えば、素直な気持ちで何度も何度も読み返し、自分がその本を生きるつもりで読む。本との付き合い方のひとつ。良い本でした。2019/02/27