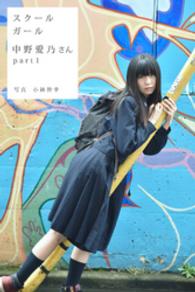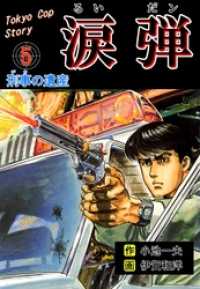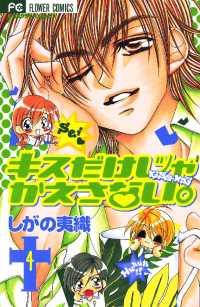内容説明
「格付け」の評価を巡り、単なる意見の表明に過ぎないとする格付会社と、それに反発する金融機関との間に軋轢が生じつつあったバブル期の日本。若き銀行マン・乾慎介、生保社員・沢野寛司、格付会社アナリスト・水野良子らそれぞれの波乱に満ちた生きざまを通して、日本を揺るがした金融危機の実相と格付会社の興亡を迫真の筆致で描く話題作!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
幹事検定1級
22
黒木さん得意の金融小説、時代はバブルからバブル崩壊あたりを実話をフィクション化させています。当時は何もわからないまま漠然とニュースを聞いていますが、こうやって本の世界で少しばかり勉強させて頂くことは私に取って大変有り難いですね。さて下巻に進みます。2018/04/04
ヤギ郎
15
プロローグは、マイケル・サミュエルズ監督『リーマン・ブラザーズ最後の四日間』で象徴的に描かれている、FRBにて行われた金融トップの会談を描く。物語の始まりはリーマン・ショックが起こる30年ほど前、日本に「格付」が浸透しまじめたことである。金融のブームも外国(欧米)と共に流れてくる。外資系と日系格付会社の成長と格付の社会的意義をみる。主人公たちよりも、彼らの周りにいる人たちが魅力的。2020/03/02
sayan
14
「リーマンブラザーズ最後の4日間(映画)」の象徴的な場面が本書冒頭で蘇る。時の財務長官ヘンリーポールセンを描写した重々しい場面はとても印象的だ。勝手に「格付け」して、どうしてビジネスになるのだろうと、素朴な疑問を持っていた。本書はそんなど素人の疑問に先回りし、登場人物セリフや心理描写から、格付け会社の存在意義や社会での位置づけをクリアにしてくれる。飲食店等で問題になる格付けサイトとは一線を介す。その専門性や葛藤が明らかになる。また、時の企業破綻事件を取り込みながら物語が展開するため、非常に臨場感があった。2019/11/04
さとむ
10
過去の事件・事実をベースに実名と別名の人物を織り交ぜて小説にしていく手法が、フィクションとノンフィクションを絶妙なバランスで溶け合わせる。読み手としてはリアル感たっぷりで面白い。格付の仕組みについても丁寧な説明があるので、予備知識なくても楽しめた。下巻にも期待大。2014/04/27
nekozuki
5
思ったよりストファイが出てこなかった…。 バブル期の金融界を描いた小説はたくさんあるけど、格付会社にフォーカスしたものはあまりないんじゃないかな? 格付はあくまで「意見の表明である」という主張には違和感がある。 その格付で金を取ってるんだから、一定の責任を負ってしかるべきでは?2015/07/20