内容説明
「情報テクノロジーの支配する社会で、もっとも痩せているのが「文学の言葉」です。私は永く「文学の言葉」で生きてきました。いまも注意深く見れば創られている、力にみちた「文学の言葉」を、知的な共通の場所へ推し立てたいのです」大江健三郎――2007年から8年間にわたり大江健三郎一人によって選考された「大江健三郎賞」の全選考過程と受賞理由、および受賞者との対談を収録した、完全保存版!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
miori
15
八回で幕をとじた大江健三郎賞受賞作の選評と、選者である大江健三郎と受賞者の対談。どこまでホンネを言ってるのかはわからないですが、それぞれの小説観が伝わってきて、満足の一冊でした。八作の内、既読が二冊、積読が二冊あるので、まずは積読の解消に励みたいと思います。2022/08/08
tomonokko
14
受賞作のうち既読は2冊。大江健三郎賞ということを意識して手にしたのではなかったので、大江さんがこの賞がどういった経緯で作られ、どのような意図をもって受賞作を選ばれたのかが、受賞者との対話を通して繰り返されることにより理解できた。星野智幸さんの章で、現在の不気味なものが膨張する日本社会のことについて言及されており、自分の中でうまく消化できずにいたものが言語化され腑に落ちる。社会に対して文学で声をあげることの意義。せめてこの章だけでも何度も再読したい。2018/10/18
いちの
7
すごく面白かった。文学を愛し現状を憂い「文学の言葉」を恢復させるために動くエネルギー。これこそ、岩城けいさんがいう「昭和10年代の方の持つ熱さ」な気がする。この本を読んでいると、大江さんが味方してくれているような感覚になって気持ちが落ち着く。大江賞受賞作は何作か読んだのにご本人の作品は読んだことがない。これはまずい。すぐに読みたい。2019/10/30
いのふみ
7
社会や認識をリードしてきた「文学の言葉」がいま、衰退している。注意深く見れば、まだ書かれているその言葉を陽のあたるところへ推し出したい。この問題意識は他人事とは思えない。家を出て楽しいことがあるのと、本の中に楽しいことがあるのとでは、間違いなく本を選ぶ。古なじみの本を読むことしか人生の楽しみがない。これを堂々と言える大江さんはすごいと思うし、圧倒的な存在感がある。受賞者の質問に寄り添うように答え、受賞者も作品について真摯に答える空気感が微笑ましい。2019/08/08
とむ
3
とても興味深く、豊かな内容だった。 この本の存在をしり、8人の素晴らしい作家に出会い、8作品を読み(光の曼荼羅だけ難しくくてまだ途中まででこれから最後まで読む)、可逆的な時間と不可逆的な時間の事のことを知ったり、小説とは何かを考え、今自分が生きている日本について考えた。途方もないようにも感じたけど、それでも考えつづけてこの時代を生きている人間の言葉にして、表現し続ける事が大事なんじゃないかと思った。今年の夏休みは多種多様な作品に出会えて幸せだったなあ。2025/08/27
-
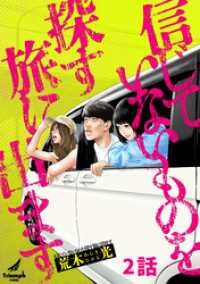
- 電子書籍
- 信じていないものを探す旅に出ます 2話…
-
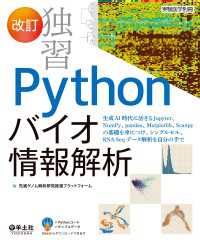
- 電子書籍
- 改訂 独習Pythonバイオ情報解析 …
-

- 電子書籍
- 女子寮の寝室【タテヨミ】♯1 picc…
-

- 電子書籍
- 戦後福井県都市計画の軌跡
-
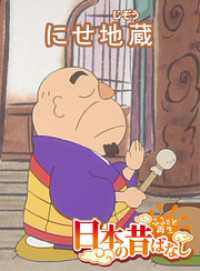
- 電子書籍
- 「日本の昔ばなし」 にせ地蔵【フルカラ…




