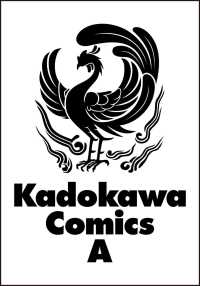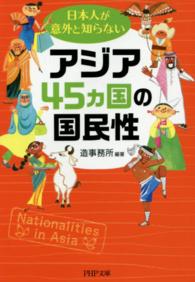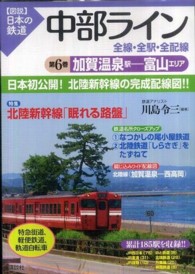内容説明
1969年、漱石論で文芸評論家として出発した著者が、『日本近代文学の起源』を経て85年の『探究』連載を前に格闘した、哲学的評論「内省と遡行」と「言語・数・貨幣」。否定に否定を重ねながら、〈内部〉に留まることを徹底して〈内部〉を自壊に導き、〈外部〉へ出ることをめざした本書は思想家誕生の軌跡であり、「驚くべき戦争の記録」(浅田彰)でもある。極限まで思考する凄味に満ちた名著。
目次
内省と遡行
言語・数・貨幣
付論 転回のための八章
あとがき
学術文庫版解説 浅田彰
文芸文庫版あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
41
『内省と遡行』-いきなり「現象学的-構造主義的還元」という言葉が使われていて、かなり驚きます。アカデミックな議論からは程遠く、全く評価しない立場もあり得ます。他方で、連想の鋭さに乗っていければ、意外と楽しく読むこともできます。構造は主体の問題を見落としている。外部をみるならば、まず内部の問題を徹底化すべきである。上位と下位、深層と表層、時間と空間、思考と表現を徹底化することにより、アカデミックな議論では到達できない位相での批判を模索していきます。一見して近代批判のようですが、ポスト・モダン思想も含めた大き2019/05/04
しゅん
8
西洋哲学の内面優位性(内省)を批判する(遡行する)には、内省を徹底することでしか達せない。ニーチェとフッサールを対置しながら、その内省の徹底を「詩的」に描かず、形式論理的に描こうとする本書は、しかしその記述自体がまた一つの「詩」ではないかという疑いを抱かせる。本書の参照先は言語学・人類学・数学・精神分析・経済学と多岐にわたっており、そこに共通の構図とズレの運動を見出していくのだが、参照先の移動が結果「内省の徹底」にも「近代西洋哲学の批判」にも通じず、むしろ両者を温存しているように感じられた。2020/10/05
tyfk
3
『言語・数・貨幣』は、2章が代数的構造、3章が順序構造だけど、位相的構造はないのね。「ドゥルーズは「構造主義は、場所がそれを占めるものに優越すると考える新しい超越論的哲学と分かちがたい」と言ったが」とか「ドゥルーズ=ガタリによれば、にせの多様体であり」とか。代数的構造については、群論の単位元がゼロ記号に対応するとしてるが、再読してみたら、むしろバルトの「浮遊するシニフィアン」「空虚な記号」が興味深く思えてきた。2024/12/19
yoyogi kazuo
2
自分が高校生くらいの時にゲーデルの不確定原理が流行っていたのを思い出した。教師たちがこういうのを得意げに読んでいた。この時に現代思想を気に入らないと思ったのが運の尽きだった。改めてこの歳になって読んでも別にいいとも思わない。2024/06/26
2
再読。中期、柄谷の代表作と言っていい。この極限的な内省/解体は、ある意味では行き詰まりに達したと言っていい。ただ、確かに柄谷の論述が愚直に推し進めているというよりは、その論述それ自体が絶えず移動して中心をずらされている(だから、他の著作に比べて明快ではないし読みづらさが半端ない)むしろ、この行き詰まりを打開するために、「教える-学ぶ」(言語ゲーム)を導入せざるを得ないのだが、確かに倫理的な後退であったと言えなくもないし、これに対しての乗り越えの可能性を東浩紀の『郵便的、存在論的』だったのではないかと思う。2023/01/16
-
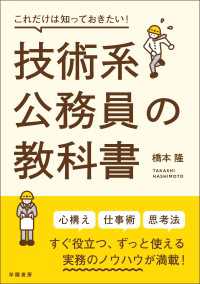
- 電子書籍
- これだけは知っておきたい!技術系公務員…