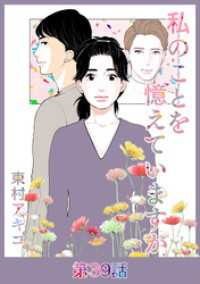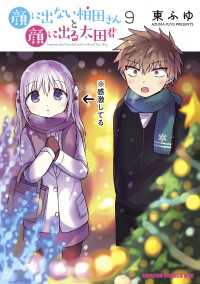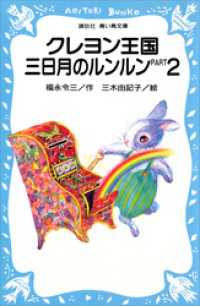内容説明
大正から昭和へと時代が移り変わる激動のさなか、検閲の嵐が文学を直撃する。円本(文学全集)誕生の経緯も交えながら、文学者、編集者、出版社が織り成す苦闘のドラマを活写する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
可兒
4
おおむね否定的なイメージが語られるだけで終わっているような「検閲」について、システムや当時の実情を詳説。教科書検定を批判したり、小林多喜二の最後について「虐殺」という語ををすらりと常識のごとく使ったり、いろいろと気分が萎れる書き方だが、内容はとても興味深い2010/01/16
ちあき
1
意外に知られていない検閲という制度の運用実態を知ることができる本。検閲と自主規制の境界がぼやけたり引きなおされたりねじれたりしていく過程が読みごたえあった。メディア関係者と昭和史好きは佐藤卓己『言論統制』とあわせてぜひ読んでおきたい。河出ブックス第1回配本6点のうちの一冊だが、このレベルをキープしながら新しい書き手を発掘できれば、新書ブームに見切りをつけて選書という形を選択したこと、「歴史」という切り口を意識したやや地味なラインナップにしたことをいい結果につなげられると思う。2009/11/10
rbyawa
0
h083、前に検閲コレクションを主体にした検閲本を読んだが、戦後かなりの部分が焼かれてしまったということで欠けている時代があり、別系統の資料から導き出されたのがこの本、ということかな。出版を巡る事情は詳しかったものの、演劇周辺で起こっていた労働者でもある作家を含めた惨殺や、そもそも政治劇と非常に近かったということが触れられていないのはさすがに違和感あったかなぁ(山本有三や菊池寛は多分この文脈)。検閲に対し文士や出版社がどういう態度を取っていたかは完全に信用するものの、この展開って本当に検閲だったのかなぁ?2017/12/05
草津仁秋斗
0
これはひどいなあ。検閲ってここまで厳しいものだったのか。現代でこういう風になったら嫌だな、と真剣に感じた。2014/07/29
ぎんしょう
0
文学史的な側面はもちろんあるが、どちらかというと政治的に文学がどのような扱われ方をしていたか、という側面が大きい。様々な資料が引かれているので、資料集として非常に役立つだろうと思う。河出ブックスはそういう色を持っているのかな?2012/02/02