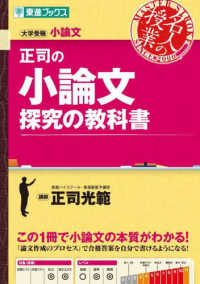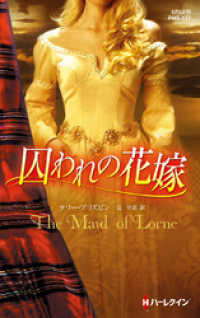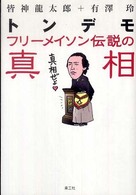内容説明
古代から現代にいたるまで、
人は「因果関係」をどう考えてきたのか?
ますます複雑化する問題にどう向き合うべきか。
古代哲学から物理科学、カオス理論まで、
先人の軌跡をたどりながら、私たちの思考の可能性と限界を問いかける。
◆ものごとの原因を考える際に「多面的な分析が必要」とはよく言われるが、
私たちは本当に「多面的に分析」ができているのでしょうか?
また、どのような手法があり、それぞれどのような長所・短所があるのでしょうか?
◆本書は、精神医学の権威が哲学や科学の歴史を踏まえたうえで、
分析と語り方のモデルを体系的に整理して、
独自のフレームワーク「三面モデル」を提唱するものです。
◆「三面モデル」は、複雑な問題について
自分の分析の観点をチェックするときに役立つでしょう。
あるいは、誰かと議論していて理解できないと感じて
自分とその人の因果性の「前提」を考える軸にもなるでしょう。
先人の思考の軌跡をたどりながら、
「思考」に対する思考を深めたい方におすすめです。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koichiro Minematsu
13
これは読み終えたんですが、手にしてから、たぶん、半年以上かかっている。何故かと言うと、ちょっと難しい(笑) 著者が精神医学長だけに、共鳴できると思ったんですが、3つのパターンでということは理解した。でも、付箋が一杯。2018/10/27
izw
11
物事の因果関係について、多面的に詳細に考察していて、単純ではないことが良く分かる。第一面は因果関係の論理を表す三つの概念モデルで、断定型、確率型、創発型。第二面は四つの分析モデルで、発生を促す原因、発生させる原因、プログラム上の原因、意図による原因。これらは、アリストテレスの原因モデルで、質料因、始動因、形相因、目的因に相当する。第三面は原因の情報を得るための三つの論法で、検証型、叙述型、進行型。これらのモデルを詳細に紹介した後、HIV/AIDS、米国法、うつ病について、モデルの適用を試みている。2018/07/12
Mc6ρ助
8
「因果」について思い込みで生きてきたようだ。本書で言う自然科学の「検証型」はよいのだが、歴史の「叙述型」はそれがあること自体目から鱗の面があった。しかし、経済学やら心理学やらも歴史と同じ「叙述型」、「語る」ものと言われると、それはそうかもしれないのだが、なかなか納得できるものではなかったよ。紹介された、卜ム ・クラウチとピー夕ー・ジャ力ブの共著 『ライ卜兄弟と空の時代の発明 (The Wright Brothers and the Inovation of the Aerial Age)』 を読みたい。2018/06/23
ケニオミ
7
これも日経新聞の書評で紹介されていた一冊です。中々面白そうと読み始めたのですが、あまり面白くありませんでした。普段だったらとっくに挫折となるところでしたが、他に読む本がなかったので、仕方なく読了です。よい教科書にはなるかもしれませんが、もう教科書を読むには年とりすぎているということでしょうか。2018/04/09
GASHOW
4
未来を語ることを鬼が笑うと言う。未来に生きている保証もない者が何を言っているんだと言うことだろう。物事の起こったあとから原因を探すことは、簡単に出来る。心理学では後知恵バイアスと言う。人の進化には情報の関連づけをずっとしてきたから、なぜかを探すのは得意だと思う。原因を探すことは多いが答えにたどり着くことは難しい。原因はシンプルではなく深さも広さもいろいろある。増税の軽減税のための施策で、ポイント還元やイートインなどの案の国民には不合理なことも財務官僚の天下り先の確保には適していて下僕の国民には止められない2018/10/17