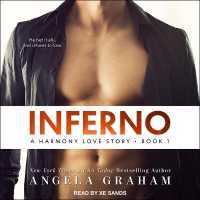内容説明
わたしはもともと、陸上競技どころか、スポーツ全般にほとんど興味を持っていませんでした。
サラリーマンだった夫が突然、会社を辞めて、箱根駅伝出場を目指す東京の青山学院大学陸上競技部の監督になると言いだしたのです。
その当時、箱根駅伝が、出雲駅伝、全日本大学駅伝に並ぶ大学3大駅伝のひとつであるとか、そういうことを、一切、知りませんでした。
当然、大学の陸上部の監督という職業、その学生が暮らす寮の寮母という職業があることも知りませんでした。
箱根駅伝に出場させること、そして優勝に導くことは、当時のわたし自身の夢やミッションではありませんでした。
でも、本気の彼らの近くにいて、支えている間に、わたしなりに工夫し努力して支え、走らせること、勝たせることが、わたしの夢にもミッションにもなりました。
これは想像ですが、わたしのように、自分が積極的に望んだわけではないのに、いつの間にか誰かの夢やミッションに巻き込まれ、
それを支えることを仕事とし、いつしか、そこに喜びを感じる人は少なくないのではないかと思います。
巻き込まれ、ふり回され、流されて、自分が思い描いていたのとは違う人生を生きることになっても、そこで自分なりに、精一杯頑張っていれば楽しくもなるよ、
とお伝えすることは、もしかすると誰かの支えになるかもしれないと考えました。
わたしの書くものが誰かのお役に立つことがあるのかなと疑問にも思ったのですが、読んで下さった方にわずかでも「そういう考え方もあるかもね」と思ってもらえればうれしいです。
<もくじ>
プロローグ
第1章 わたしたちはみんな、誰かを支えるために生きている。
第2章 誰にも見向きにされないときに一生懸命考える人たちが「伝統の根っ子」をつくった。
第3章 いいチームができると「火事場のバカ力」が出せるようになる。
第4章 わがままな夫だからこそ楽しい。男はちょっとわがままな方がいい!?
第5章 与えられたことでも、喜びに変わる瞬間は来る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kurara
ぐっち
Sato
わんつーろっく
ルート
-
- 洋書
- Inferno