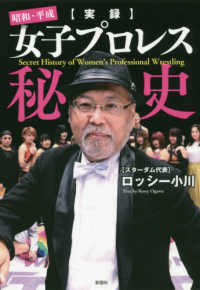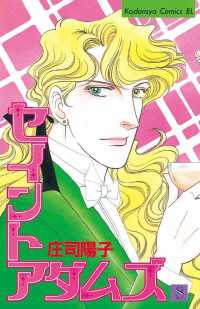- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
これまでにない長い老後を生きる時代が到来した現代、人は老いとどのように向き合えばいいのか。さりげない表現の中に現代日本人の老いを描く幸田文。島崎藤村が綴る老後の豊富さと老いることの難しさ。伊藤整が光を当てた老いの欲望と快楽。伊藤信吉が記す90代の老年詩集……。文学作品・映画・演劇に描かれたさまざまな老いの形をとおして、現代に生きる者にとっての<老い>の意味と可能性を追究する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
27
介護の概念は昔からあるが、今あるそれはビジネスの様相を呈している。その対象であるの一つである老。これは概念論と思ったが、古今東西の文学、作家を冷徹な視線で見据えた作品だった。執筆時の筆者は74歳。本文中にあるように「老いを受け入れる時期」にあり、真摯に自己認識しつつ書いたであろう内容を感じる。キケロから始まり伊藤信吉まで扱った14章は簡潔ながらも、醒めた無駄のない文章、脳裏に染み込んで行く。芥川・太宰・志賀・清張・藤村が「老い」に向ける想いは昔断片的に読んだ記憶があり、おさらいする感じ。2014/01/30
イカ
4
老いについて、14の文学や映画を題材にして一つずつ丁寧に考察していく。文学的、哲学的に深く考えることを楽しめる。こうだという答えは示されない。「老いは多面的であり、謎を秘め、容易には正体を掴みがたい…老いはある日突然に訪れるものではなく、そこまで生きてきた結果として人の前に徐々に姿を現す…老いの一般論などというものはないと断念するところから、自分自身の固有の老いへの独自の模索が始まる…老いは過去と切断された時間ではないと同時に、また現在進行形の時間でもある」。2020/02/03
Hiroki Nishizumi
3
まだ、この手の本を読むのは悲しいけど仕方ないという思いがある。内容は悪くないが、今は馴染みたくない気持ちの方が大きいと言う矛盾を抱えつつ読了した。2017/02/13
おらひらお
3
2006年初版。まだまだ老人には程遠いのですが、30代でも読むに値する本と言えそうです。ただ、精神面や身体面の話が多く、金銭面の話がなかったのは少し気がかりですが・・・。年とってお金がなければ結構きつそうな気もします。2012/09/05
jupiter68
2
やはり定年を迎え、今後のことを考える時間が多くなってきた。今回の本はそのまま老いを受け入れる内容となっている。多くの書籍などを紹介していもらっているので、参考になる。今はいいが体調不良の期間が長い人生はつまらん。健康で動けることが一番いい。2022/08/31