内容説明
ソシュールからウィトゲンシュタインへ、西田幾多郎からスピノザへ──。1980年代後半の代表的講演を収録した本書で、柄谷は哲学、文学、宗教、言語学、経済学、数学など多様な領野を自在に行き来しつつ議論を繰り広げる。そこで執拗に追求されるのは、言語コミュニケーション(交換)における人間の悲劇的条件であり、他者との交通を可能にする普遍性がいかに生み出されうるかという問いである。いまなお多くの示唆に満ちたこれらの講演は、後の柄谷理論の展開を予感させるのみならず、批評という営み自体をも再審に付す魅力的な内容となっている。旧版の内容を再構成し、改稿を加えた決定版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
33
沈思黙考し、冷静沈着に「思考マシーン」として思考を練り、そこから『内省と遡行』『探究』I・IIなどを刊行した柄谷行人がいる。それらはいずれも瞠目すべき成果だろう。だが、彼はけっしてそうした「内省」に自足してしまう批評家ではなくむしろ外に出て、そこから外部と交わりコミュニケーション(「交通」?)を試し続ける活動家でもあった。この講演集を読むと、まだ海外で活躍することがめずらしかった時代からポール・ド・マンやジャック・デリダといった思想家たちと交わり、みずからを絶えず更新させつづける姿がうかがえる。スリリング2025/04/20
踊る猫
29
柄谷行人を読むとはどういうことなのか考え込んでしまう。柄谷の思考を自分なりに敷衍して好き勝手に(口真似で)語るべきか、それともここは柄谷にならってきっちり修練を積むべきか。ぼくはずっとこれまで前者のスタンスで(どうせ難解な哲学などわかるわけがないと思って)本を読んできた。だが、それは柄谷のタームで言えば「他者」「外部」を持たない思考の作法ということになるのだろう。でも、だったらどの時点で柄谷なら柄谷の思考は自分のものとなったと言えるのか。どのように理解しても常に誤読・誤解の可能性がある……そんなことを思う2023/09/09
踊る猫
26
頭脳派の思考マシーン、という印象があった柄谷。だが、この講演集を読み返してみるとデカルトやスピノザ、ニーチェの哲学の身体感覚、そして「この私」「他者」との関係から生じる生理的なディスコミュニケーションへの違和感をテツガクとして昇華していることがわかる。つまり、柄谷は結構肉体派なのではないか。柄谷がバスケットボールの選手だったことは聞いたことがあるが、実は思考を駆使するにあたって自分の実感から立ち上がるものを素朴に考察の遡上に載せて、そこから自分の感情/情念を整理しようとしていることが伺える。そこが興味深い2020/07/01
またの名
13
「男/女なんて他にいくらでもいるよ」と言われても取り替えられない「この人」を失った失恋の悲しみに沈んでた人間が、半年も経たずに別のこの人を見つけリア充ライフに戻る、単独性と一般化可能な個別性との揺れ。単独性と唯一それを示す固有名、共同体に同化され得ない他者、デカルトやスピノザの独自解釈など探求シリーズで論じていた事柄を、噛み砕いて説明している講演集。次々と生成する日本の古層を論じたがった国学者たちから丸山眞男やフェミニストまでをも、どこの共同体でも生成論を持つと言い切って一掃する切れ味の鋭さが全編に出現。2019/03/19
ずー
1
『政治、あるいは批評としての広告』目当てで読んだが他のところも面白かった。「共同体」の思考から抜け出すことというのが通底するキーワードになっているように思うが、2022年現在読むと今の日本の”保守”化への警鐘としても受け取れるものがあるように感じた。 ”ファシズムには、大衆を魅きつける何かがあった。それを忘れることのほうが危険ですね。”2022/12/24
-

- 電子書籍
- 救国の十三装星者、破壊の災いを滅す【タ…
-

- 電子書籍
- 英雄詐欺 弟子が最強だからって師匠まで…
-

- 電子書籍
- ヤングキングラムダ5号
-
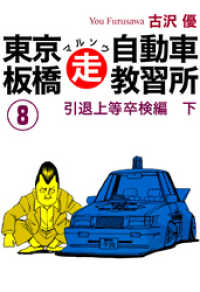
- 電子書籍
- 東京板橋マルソウ自動車教習所(8) ゴ…
-
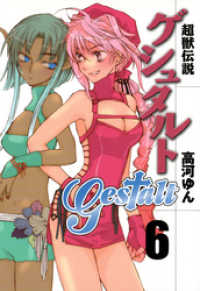
- 電子書籍
- 超獣伝説ゲシュタルト: 6 ZERO-…




