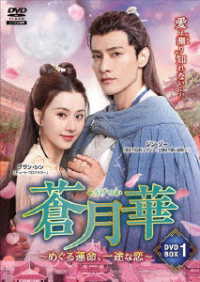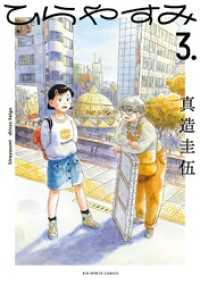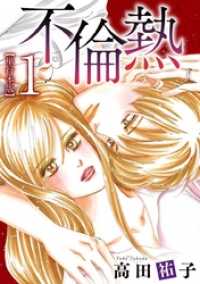内容説明
大災厄に見舞われ、外来語も自動車もインターネットもなくなり鎖国状態の日本。老人は百歳を過ぎても健康だが子どもは学校に通う体力もない。義郎は身体が弱い曾孫の無名が心配でならない。無名は「献灯使」として日本から旅立つ運命に。大きな反響を呼んだ表題作のほか、震災後文学の頂点とも言える全5編を収録。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
青乃108号
266
ドグラ・マグラ以上に狂った本。一応、意味は読み取れる文章も読んでるうちに段々狂って来て献灯仕はいつまで経っても献灯されないし、あれ本の半分読んでるのに、これって短編集じゃなかったのか、そうか、目次のタイトルは章のタイトルだったのね、長編小説だったのね、きっついわー、と思っていたら唐突に終わって、何だやっぱり短編集だったじゃないですか。しかし次の短編も、又次の短編も、絶対即興で書いてるよね、これ。一応、震災後って共通のテーマだけ決めて、思い付くまま気の向くまま、行き着くところはキーボードに聞いてくれ。無理。2025/03/01
はっせー
185
かなり考えさせられる本であった! この本、献灯使はディストピア小説である。大災厄に見舞われて、鎖国政策を復活させた日本における曾祖父と曾孫との話である。長生きしている曾祖父は曾孫のことが心配で心配でしょうがないのである。この世界は東京23区の価値が完全になくなってしまっている。東北や沖縄のほうが価値がある世の中。そんな世の中で東京西部に住むことは並大抵ではない。食べ物を自給自足することは大変でことであり、本当にこんな世の中が来てしまうのかと想像してしまう。本当にリアルな部分はリアルなので、想像しやすい。2019/08/13
ちなぽむ and ぽむの助 @ 休止中
183
こういうディストピア的なお話は読むのがつらいが、多和田さんの作品ということで挑戦。なんとも実験的な小説、というのが最初の感想。 遠い昔の大災厄を受け各国は鎖国状態。老人は死ぬことなく、脆弱な若者の介護をして生きている。外来語の使用は法律で禁止され、作物の育たない東京は人のいない街に。機械は排除され、人々はむしろ昔ながらの生活で細々と暮らしている。全体から漂ってくるそこはかとない恐ろしさ、諦念。かなしみ。言語の変遷と、大衆におもねる様々な事柄。特に休日のくだりなんかは印象的だったので引用。2019/02/27
mukimi
131
村上春樹と並びノーベル賞候補になっている日本人作家がいると知り読んだ。ずっと飲み下せない灰色のホルモンを噛み続けているような気持ち悪さがあった。しかしこの不気味さの中に1%の愛しさを見出すことができればきっと救われたと感じることができる。絶望の淵にある心を救い日常の不条理に疲弊した心を癒すのは、美しいものばかりではない。孤独や違和感や怒りの共有だったりする。それが文学という芸術のなせる技だと考えた。筆者は救いも癒しも与える気はないのかもしれないけれど。こんな感想をもつ一読者を軽率と思うかもしれないけれど。2025/11/03
ケンイチミズバ
131
大きな破局から一定の時間が経過した世界。この国の破局を自分達がちゃんとしなかったからだと、現状への後悔と責任を痛感する老人の姿は私達読者に向けられている。退化し生命力の薄い若者の面倒をみる曾祖父。孫はちゃかして自分達をイゾンビと呼ぶ。野菜が育たなくなくなった関東は沖縄と貿易をしたりしている。少しでも安全なものを曾孫に食べさせたい。責任を感じている老人は死ねない、死なない。百歳を超えて弱い若者の介護のために強くたくましく生きている。なんたる矛盾。文学的な示唆に富み難解でもある。強い個性も感じた。2017/08/28