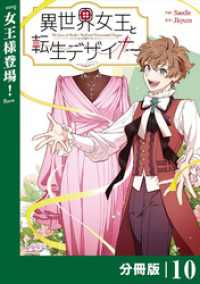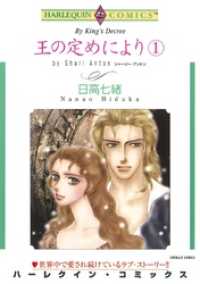- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
今後10年以内に65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると予測されている。認知症はもう誰もがなりうるもので、また誰もが認知症の家族のケアに直面する可能性がある時代となったのだ。著者は、認知症治療の課題に、医師の言うがままに多量の薬を服用し続ける「多剤併用」や、処方薬を飲みきれずに捨てる「残薬」などの問題を挙げる。家族、医師、薬剤師、ケアマネジャーなどがチームとなって患者を支える「在宅医療」の具体的なあり方も提唱し、認知症患者と家族に寄り添う医療を考える。【目次】まえがき/第1章 認知症は誤解されている/第2章 認知症はもう他人事ではない/第3章 不適切な薬物療法が認知症をつくりだす/第4章 家族は在宅医療にどう向きあえばいいのか/あとがき
目次
まえがき
第1章 認知症は誤解されている
第2章 認知症はもう他人事ではない
第3章 不適切な薬物療法が認知症をつくりだす
第4章 家族は在宅医療にどう向きあえばいいのか
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Akira Kumoi
5
ケアと薬の最適化、特に先生がかねてから指摘されている多剤併用の問題について易しい言葉で解説されておられ、わかりやすく読めました。また理想とする医療のイメージを「地域にとろけるような」と表現されていたのは、髙瀬先生の在宅医療への想いや姿勢がストレートに伝わって印象に残りました。2017/02/25
ゆきまさくん
1
再読。高瀬義昌先生の書。認知症は病名ではなく症状であること、そして誰もがなりうるということ、さらには誰もが認知症の家族のケアに直面する可能性があるということだ。この本では、薬の最適化、在宅での患者を主役とするケアの最適化、家族のマネジメント力による認知症の改善の可能性を述べている。国が進める在宅医療の流れを理解しつつ、本書にある認知障害の改善や予防に効果がある食や取り組みを参考にしたい。2019/06/02
Hisashi Tokunaga
0
もしも認知症発症のときが訪れてしまったら、誰にも遠慮することなく医師や様々な社会の仕組みにどんどん頼ってーと高瀬先生の心強いエールをいただくのだが、実はここに高瀬先生の逆説が込めれていないか?正に地域社会に溶け込むだけでなく”とろけ込む”関係性が今構築されなけばならない。「認知症スマートシティ」はスマートシティ構想の総体の中に位置付けられて実現されることを願いたい。*薬物療法ー多剤併用⇒不適切な薬物療法が認知症を作り出すとの警告。2017/07/07
こ~じぃ。。
0
多剤併用や残薬にスポットを当てられているが、、 そこじゃないんじゃないかなぁ・・・2017/04/17
mieken
0
在宅医療の医師が書いた本。薬の適切な使用により、本人も家族も家で穏やかに暮らすことができる、と述べている。2018/02/26