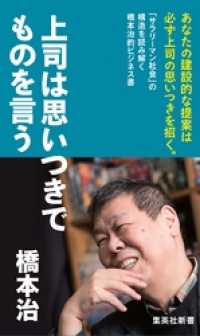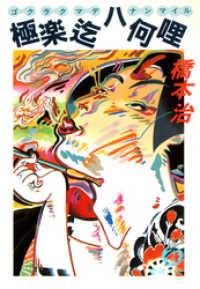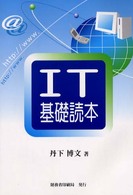- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
『日本の行く道』というタイトルを見ると、人は「これからの日本の行く道を教えてくれる教科書のようなものだ」と考えるでしょう。そして人は「教科書のような顔をした本」を求めます。なぜなら「教科書ならよっかかれる。だから安心だ」と思うからです。しかしこの安心は、生きるための選択肢を狭めることです――こうした意識のもとで、作家・橋本治が「教育」「家」「政治」「経済」のことどもに、独自の「一発かませる」を展開する本です。【目次】はじめに/第一章 「子供の問題」で「大人の問題」を考えてみる/第二章 「教育」の周辺にあったもの/第三章 いきなりの結論/第四章 「家」を考える/あとがき――二十年しか歴史がないと
目次
はじめに
第一章 「子供の問題」で「大人の問題」を考えてみる
第二章 「教育」の周辺にあったもの
第三章 いきなりの結論
第四章 「家」を考える
あとがき――二十年しか歴史がないと
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
太田青磁
16
なんだかまとまりはないんだけど、言ってることは共感できる。いじめによる自殺と親による虐待の結果の死の類似には、社会の閉塞感を感じます。家と学校以外の居場所がある子どもは幸せなのかもしれません。プラザ合意からのバブルはなんだかなあと思いますし、西欧列強の襲撃を受けた薩長という地域とその官僚体制が現在の政権まで影響を及ぼしている現実は不思議な気分です。60年代に戻すのが解であるのならば、日本の60年代と同じような道を辿っている国や地方に活力を見出せということなのかもしれません。2013/05/15
1.3manen
13
今の日本は何かおかしい・・・。そういう漠たる不安を抱いていたところ、3・11が発生したのではないか。本書は、6年前に出ている。しかし、色褪せない。子供による他の子供への虐待、それが、いじめ(28頁~)。虐待とは、親が子を、というばかりではない。同じ境遇でも虐待が起きる。自明のことのようでいて、見過ごす点だ。いじめは、逃げ場をつくらせない。姑息なやり方である。いじめは、本音と建て前の文化から生み出されているのではないか。評者はそう思う。外面と家では二重人格。そんな親も多いのではないか。村八分の追放もいじめ。2013/07/07
おせきはん
12
今は、そのように感じることがよくありますが、この本が出版された10年余り前に既に「思いやりが足りない」と書かれていたことが特に印象に残りました。子どもの居場所が家か学校の二択で、その他がなくなったのは大人も同様で、その結果、サード・プレイスが注目されるようになったのでしょう。今から10年後、日本がどのようになるか、自分なりに考えを巡らせてみたくなりました。2018/01/05
Hiroyuki SATO
11
https://what-is-this-is-it.blogspot.com/2018/10/blog-post_36.html 印象に残っているのは、「高層ビルなんていらない」って感じかな。確かに、人口が減少した未来の日本で、果たして維持できるのだろう?2018/10/14
阿部義彦
11
扱う範囲が広すぎてとても要約できません。産業革命や終身雇用やエコロジーやその他諸々を橋本治がまたややこしく一点突破します。なんと、文明をあの時代なみに戻してしまえば如何とばかりに高層ビルディングを壊してしまえと暴論を展開!あとは自分で読んでややこしくなってください。2016/01/30