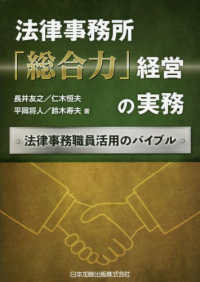内容説明
食の先覚者・薩摩鹿児島から、馬肉・昆虫食の木曽信濃、山鍋と海鍋が併存する秋田へ。風土と歴史が生み出す郷土食はどう形成され、どう変貌したのか。日本全国、見て飲んで食べ尽くして考える旅のエッセイ。
『日本ふーど記』を改題し、〈改版にあたって〉を付しました。
《目次》
薩摩鹿児島――幸あり南方より来たる
群馬下仁田――コンニャク・エネルギー不変の法則
瀬戸内讃岐――パスタ文化食べ歩きリサーチ
若狭近江――頽廃の美味は古きワインで
北海道――国境演歌味覚変幻
土佐高知――初鰹たたく気分は“いごっそう”
岩手三陸――日本ホヤスピタリティー考
木曾信濃――何でも食べてやろう
秋田金沢日本海――山と里なべもの裏オモテ
博多長崎――ちゃんぽんと唐様で書く三代目
松阪熊野――ふだらく赴粥飯法
エピローグ/東京――二〇〇年前のファースト・フード
文庫版あとがき
改版にあたって
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Akihiro Nishio
19
飲み屋で一人本を読むのにはこういう本が適している。少しずつ読み進めてようやく読了。各地を旅しながら食に関する歴史や現地の人の考え方を探るという構成。改定は2017年だが初版は1988年。だいぶ世の中は変わったが、食については30年前に危惧したほど悪くならなかったかもしれない。筆者は1983年に長野県に移住し、様々な野菜を生産しているので、生産や流通をしっかり把握しており、考察の奥行きが深い。自分も畑をやっていたこともあるが、夏に大きな出張が入るようになってやめてしまった。筆者のような生活に憧れる。2018/04/16
夜郎自大
7
郷土料理の生い立ちをめぐる旅。地理や気候によってそこで採れる食材が決まってしまう。そこに人間の知恵と流れる時間量で調理方法が積み重なって郷土料理となった。それが物流や人流で色々と混ぜ合わさって今の食事情があるんだな。2021/11/21
ぶうたん
6
本書の中に若狭の方言で怖しいを「京都い」と言うと書いてある。岩井志麻子で岡山の「きょうてぃ」を知った口であるが、音が良く似てるのが気になる。岡山のきょうてぃも京都が怖いから生まれたのだろうか。両側から怖しいと言われるほど、京都は怖いのか?で、話はそれたが、内容は食べ物エッセイであり、色々と興味深いし食欲も唆られる。ただ、著者の興味はそれだけでなく、文化の伝搬から縄文弥生の話まで脱線することもあり、そんなところも面白い。2024/06/20
まぶぜたろう
5
4月くらいからチビチビ読んできて、ようやく読了。■流石、玉村豊男、食の記述はやたら美味そうなのだが、日本の食文化、食の歴史に筆の多くを割いており、この店が美味しい、この郷土料理は絶品、みたいな記述だけを求める私のような通俗者にはいささか退屈であった。チビチビ読むにはいいんだけどね。2021/05/22
りょう
2
80年代の本だけど、本質は変わってないと思う。都会が崩壊していって、田舎も、徐々に壊れてるのかなあ。2017/03/15
-

- 電子書籍
- 自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲ…
-
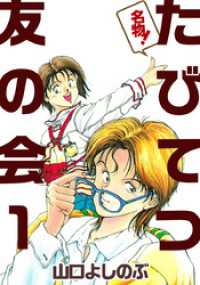
- 電子書籍
- 名物!たびてつ友の会 1巻 まんがフリ…