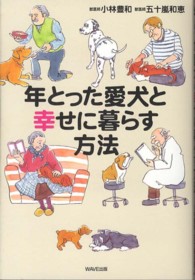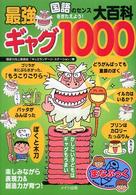内容説明
京都・奈良の寺社が巧みに地形を利用したさまが即座に把握できる! 地形の凸凹を立体的に地図で表現して読み解く本は数あれど、より大きな縮尺で模型にすると、迫力ある、地形と建物の関係が見えてくる。本書は、世界遺産となっている寺社中心に、京都と奈良、紀伊山地のそれを建築模型的に立体的に造形し、そこに建物の位置や「世界遺産のコアゾーン(資産)」を記すことで、寺社や周辺がどのように地形と関わって来たかを読み解いていく。補助的に凸凹地図も多く使用している。合わせて、建築史や庭園史も概観し、京都や奈良の寺社への理解がより深まる。リピーターにこそ手にとって欲しい本。■第1章 地形の読み方 1山河襟帯で読む-地形を断面で読む 2凸凹地形で読む-地形を平面で読む 3都市を凸凹地形で読む■第2章 京都の世界遺産 世界遺産でたどれる建築史・造園史/地形を彩る五つの境内 1清水寺 2伏見稲荷大社-奥山の境内 3金閣寺、銀閣寺・西芳寺-テラス式庭園 4仁和寺・宇治上神社-テラス式伽藍・建物 5上賀茂神社・下鴨神社-川の境内/凸凹地形のユニバーサルデザインと径間 1境内における車イスアクセス 2様式-和風か現代風か■第3章 奈良の世界遺産 1都市と地形 2春日大社・興福寺 3東大寺■第4章 世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道 熊野三山・高野山■第5章 古代・中世から近世、そして現代へ-地形の読み方から活かし方へ 1近世 2現代
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
3
国土地理院の数値地図を元に作成した地形模型による世界遺産の立地や高低差を利用した建造物、庭園を読み解いた、有るようでない本。清水寺の舞台は巨大な岩盤の上に作られた、仏教以前の磐座聖地を取り込んだ仏教の施設であることを立証しており、蒙を啓かれた。高低差の配置が宗教施設の荘厳さを演出している事に、空恐ろしさを感じた。厚紙を切り抜いて模型を作成した著者ゼミの学生さんたちに敬意を表したくなる。2017/05/03
竜玄葉潤
2
地形と建築物の関係を、立体模型を使って解説。その取り組みや考え方は最高でした。ただ、残念ながら本としては読み辛い、建築家の人が書いているのだから、編集者が何とかして欲しかった。2017/09/12
ひ※ろ
1
★★★☆☆2017/04/02
-
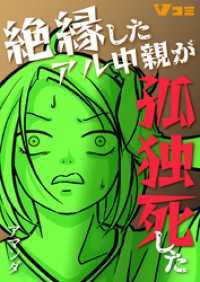
- 電子書籍
- 絶縁したアル中親が孤独死した1 Vコミ