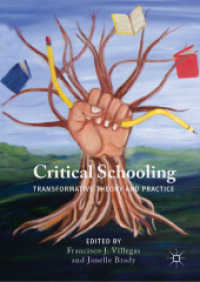- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
そもそも食料は、市場経済には馴染まない
今こそ、TPP上陸に当たり、わが国の「食」を防衛することが、第一優先の時を迎えています。
そもそも食料は、文明が造り出した便利な品々とは対立関係にあります。
市場が価格を決める市場経済は、利益を目的に成立しています。
利益面だけで言えば、便利な品々の場合は、たとえ原価のかかっていない粗製濫造の商品であっても買い手が納得していれば、
交換価値は成立し、売り手は大きな利益を得ることができます。
しかし、“食=命”の食料と消費者との関係は、消費者にとって食料の安定した確保と同時に、安全であることが何よりも優先されなければなりません。
そして、この本でも、述べたように、すべての争いは『食』から始まります。
世界の食料需給は逼迫しています。わが国が食料の輸入を拡大することは、世界にテロや戦争を輸出しているのと同様です。
わが国の生活者の“幸せ”を願い、平和で豊かな永続性のある国づくりのためには、「食の国際化」から脱却し「食の地域化」が絶対条件です。
今こそ、『地産地消』の出番なのです。
第1章 「食の国際化」は戦争の火種
第2章 生存率を示す食料自給率
第3章 「食育」は『地産地消』の理念
第4章 「食育」のあるべき姿
第5章 『地産地消』の生き方
第6章 豊かな暮らしのために
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
茶幸才斎
6
食料が生命維持資源であることを考慮すると、食料の流通を市場経済に委ね、TPPに代表される輸入食料の拡大政策を進める現在の「食の国際化」路線は大きな誤りで、食料の安全確保と安定供給の維持には、「食の地域化」こそが正当であり、それを実現するのが「地産地消」の推進であり、その要となるのが「産地直売所」の整備促進である、と主張している本。今や料理をしない(できない)人が都会には多いと聞く。それでは、地元で採れた新鮮な旬の食材を食べる幸せ、なんて云ってもピンと来ないだろうな。その意味でも「食育」が重要ということか。2017/02/02
Tokihiko Asahigata
3
TPP問題や地産地消、食料自給率等は別々のものとして、頭の中に内在していたが、体系的にまとまった気がする。個人的には、各国の食料自給率、地域毎の学校給食事情(自校式、センター方式なのかetc)、産地直売所の話しが面白かった。産地直売所はやりたいと思っているので、参考にしたい。2016/12/26
Kei
2
生命維持産業であるはずの農業がグローバル経済に組み込まれてしまっていることへの問題意識から、食育・地産地消による自給率の向上を説く。言いたいことは良くわかるし共感もできるが、グローバル経済そのものの構造を批判的に論じたヘレナ・ノーバーグ=ホッジの「ローカル・フューチャー」の後に読んだこともあって物足りない。また、全体的に「てにをは」レベルから日本語表現のおかしな箇所が目立ち、非常に読みづらい。さすがに編集のレベルが低いと思う。2019/01/15
ぷぅ
1
食育基本法が成立したからといって、必修科目でもないため、学校によって取り組みも曖昧。給食の地産地消も差があって、実際のところ、輸入に頼っているし、食の安全も確かではない。学校だけに頼っていないで、家庭でも食育が出来るように子どもには、いろいろと教えていきたい。2017/02/22
-

- 電子書籍
- 初めてのセンセ。(話売り) #14 ヤ…