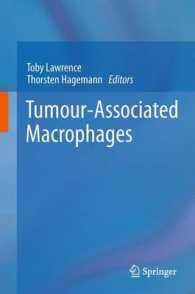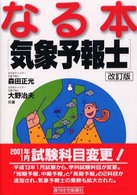内容説明
新約聖書が成立したのは、キリスト教の歴史のなかで特殊な状況が存在したからである。その歴史的に特殊な状況とはどのようなものなのか。そして新約聖書が成立して以来、新約聖書が権威あるものとして存在することが当然のように考えられているとするならば、そのような事態を当然のこととする特殊な立場が新約聖書をめぐって存在していると考えねばならないだろう。その特殊な立場とは、どのようなものなのか。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みのくま
12
初期キリスト教に聖書は存在しない。イエスは律法を乗り越える為に文字から距離を置いたし、パウロは言葉によるコミュニケーションを優先した。つまり「新約聖書」の誕生とキリスト教の誕生は全く関係がないのだ。キリスト教はユダヤ戦争後、ユダヤ教と分かれて独自の進歩を遂げる。その中で教会主流からヘレニスト、パウロ、マルキオン派、グノーシス主義、モンタノス派と多くの分派を生む。教会主流はこれらの異端を排除しつつ一部を受容する。またパウロ以降、教会はローマ帝国の世界支配の手法を取り込んでいく。そして「新約聖書」が編纂される2020/01/13
ケニオミ
11
「隠れキリシタン」であることを公言している「隠れキリシタン」として、この手の本にはついつい手が伸びてしまいます。(新手の踏み絵ではないかと勘ぐっています。)いや~あ、新約聖書の成立についてとても示唆に富む一冊でした。最初の、イエスの時代のユダヤ教に係るグループの紹介から非常に興味深く、マルコによる福音書、そしてパウロ書簡あたりまで一気に読み進みました。最後の方は少し駆け足気味でしたが、再度聖書を読んでみようかという気持ちになりました。これで「隠れキリシタン」から熱心なキリシタンに変身か!?てなことないか。2017/01/12
belier
6
イエスが生きていた頃、教えを文書に記録しようと試みた形跡はなく、死後も口承で伝えられてきた。やがて文書が残されるようになるが、ほぼギリシア語圏でのみでアラム語ではほとんど残されていない。ユダヤ戦争後に文書は乱立するようになるが、それらをまとめようという発想はなかった。異端のマルキオンが自身の教義にあった聖典を選ぼうとしたのが始まり。主流派はそれを模倣したのだ。だが何を聖典にするか意見が一致せず、確立したのは4世紀。著者が途中で叙述の流れを崩して長いパウロ批判を展開していて、それが妙に印象的だった。2023/12/16
刳森伸一
6
『新約聖書』の形成過程を原始キリスト教の変容と発展とともに描き出す。原始キリスト教については不明な点が多いので、致し方ないところではあるけれど、推論が多くなってしまうのは否めない。ただし、出来るだけ誠実に語ろうとしていて信頼できる内容だと思う。2016/11/30
maqiso
5
イエスの死後、復活を信じる弟子たちがエルサレムに共同体を作り、口頭でイエスの教えを伝えた。共同体から分離したヘレニストは新たな権威としてマルコ福音書を作る。パウロはユダヤ教と距離を取り、ローマ帝国に習った教会組織を作る。ユダヤ戦争後にローマ帝国内のキリスト教徒はユダヤ教から切り離され、独自の権威を必要としたため、福音書やパウロ書簡が選ばれた。グノーシス的なマルキオン派が正典を決めると、主流派でも聖書の確定が進む。パルチア帝国版図ではこのような動きがなく、アラム語の聖書が作られなかったと考えられる。2022/04/16