内容説明
「悪」を取りこみ、人間社会は強くなる――タスマニア人の悲劇から得た洞察の真意とは。なぜイギリスは広大なインドを容易に征服でき、しかしその統治には失敗したのか。なぜ二度の大戦で勝利を収めたアメリカが、ベトナムでは敗北したのか。稀代の国際政治学者が、若き日に世界各地で綴った珠玉の文明論。【没後二十年記念復刊】。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koji
14
略50年前の文明論ですが、古さを感じさせない名著。特に米国論は秀逸。「アメリカ人は知恵より生命力によって特徴づけられる。楽観主義に支えられた粘り強さによって文明を広めようとすることは米国の宿命。」は至言。私が最も気に入っているのは、「普通の状況においては、一糸乱れぬ集団より少々内部に不協和音を発する集団がより大きな力を発揮する」。もうひとつ、おもしろいのはタスマニア。著者の子供心を鷲掴みにしましたが、その滅亡は細菌によるもの。ただ、一つの悪に起因させるのは禁物であることを学びます。相対主義は私にも親和的。2017/08/21
Fumi Kawahara
5
「どこに行っても自分の生活習慣を変えないイギリス人と違って、その土地に同化しようとすることにおいて、より大きな努力を払うアメリカ人は、その同じ理由から、その土地をアメリカに同化させようとすることにおいても、熱心である」ってくだり、この間読んだ文明の衝突抜粋版新書と同じだなぁ・・・アメリカを世界のようにしたくて国内においては多様性を叫び、世界をアメリカのようにしたくて国際社会に自由民主主義を押し付ける・・・やっぱり国民の本質ってのは、なかなか変わらないものらしい(*´Д`)2020/12/15
さんとのれ
5
純粋に好意によって進められた進歩や援助でも破壊に行きつくしかない場合もあるし、その逆もしかり。諦念も楽観も受け入れる柔軟さがあれば、思い通りに行かなかったゴールからもセカンドベストが導き出せるだろうか。一番の悪手は、間違いを許さない潔癖さなのかも。たとえそれが善意に依るものであっても。2019/04/24
まさにい
5
この本、1968年に書かれたもの。筆者34歳の時のものである。えぇ~、34歳でここまで書けるの?何か凄い。どれだけ必死でものを考えていたのだろう。その後の筆者の本を読んでもこの本と基本的にはぶれていない。さすがです、高坂先生。筆者の没年は1996年、63歳であった。あと20年生きていたらもっとましな政治家が今いたのかもしれないと思うと残念でならない。天才も薄命なのか…。2017/08/27
Orange
5
人は心に矛盾を内包しているのだから、人がつくりだす社会は矛盾せざるをえず、ゆえに社会が抱える問題は論理や原理原則だけでは解決できない。めんどくせえ。しかしそのめんどくささやややこしさ、混沌や多様性を、この本の著者は愛しているのではないか。だからこんな本が書けるのではないか。多様性を愛するなんて、言うほど簡単じゃない。自分と違う考えや意見、異なった文化や風習をどこまで受け入れることができるのか、俺には自信がない。この著者が今の世界を見渡したら、どんなことを考えるんだろうか。2016/06/18
-

- 電子書籍
- VIP STYLE PLUS+ vol…
-
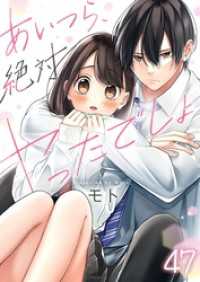
- 電子書籍
- 【フルカラー】あいつら、絶対ヤったでし…
-

- 電子書籍
- 隣の席の、五十嵐くん。 46巻 コスモス
-
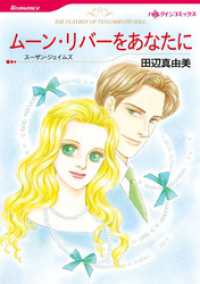
- 電子書籍
- ムーン・リバーをあなたに【分冊】 7巻…
-
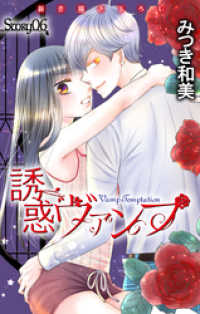
- 電子書籍
- Love Jossie 誘惑ヴァンプ …




