- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
音楽、演劇、ダンス、詩、建築、彫刻に絵画……。芸術作品とは、初めに構想(アイデア)があってそれを具現化したものだと私たちは考えがちだが、それは美の成り立ちから眼を逸らした俗流の解釈にすぎない、とアランは言う。では、どう考えるのか? 戦火のなかで書きとめた『芸術の体系』に次ぐ、アランのユニークな芸術論集。アランの斬新かつ奥深い芸術観にきっと眼を開かれるだろう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
42
20世紀の批評だと思って読むと読めない。人類学的に遡行して、各ジャンルの成立起源を考察することで、それぞれの表現の何をみたら人間の何がみえるのかを解き明かす。読み易くしようという読者への配慮があるので、鷲田清一のような身体論や人生論として読み替えて、印象に残るフレーズを記憶にとどめておく手はある。しかし現在のような題材と実証性を伴った即物的な批評ではないため、形象性のない神話を読んでいる気分にさせられて、読み続けることができない。2025/07/07
吟遊
15
アラン『芸術の体系』が構成はかなり整っていて、かつ、叙述が包括的(その分、ぶ厚い)であったのに対して、後年の講義録であるこちらは、構成も自由、一回の講義も長くはないから、途中で切れてしまう。エッセイ風のフランス・モラリスト流の筆の運びは健在で、発想のままに書かれた言葉は、やはり新鮮で、活き活きしている。だが、他方で相変わらず、前後の文脈が取りにくい。/「見世物」「衣装」にそれぞれ2章を割いているのはユニーク。軍事パレードを美しい、と評するあたりは元志願兵。屈託がない。最後の一章「芸術家」はとくに面白い。2017/01/26
たばかるB
13
アランに触れたのは初だったので、一貫した芸術論の展開に面食らった。精緻な論調で小難しい印象だけれど、それが内容に引き込ませる。難度•興味の点で再読が必要。以下は注目した点の抜粋#ダンス、詩、音楽は内面を規制しつつ表現するのに対して劇や祭りといった見世物は内面の表出を避けるようだが、真の役者は自分のアイデンティティが表現の土台だと認識する。#芸術を通した社交の営みが、個々の文脈の中で鑑賞者との記号の交換、一致、強化をもたらすことによって生きる上での喜びを生じさせる。2019/05/05
ラウリスタ~
13
アランを読むのは初めて。本書では講義形式で芸術全般についてわりと抽象的な話をする。だからぼうっと読んでいると、なにが書かれているのか分からなくなりがち。でも、言っていることはそんなに特別なことではなく、むしろ教科書的なことばかりにも思えるが。カントの助けを得て発見する「美しいものは心地よいものではない」という事実や、芸術家の頭のなかに既にある構想を表現するのが芸術ではなく、制作活動を通じて曖昧模糊としたものが形を得ることなど、まあそりゃそうでしょう、なんだけれども、大事な事だから何度でも言うべきか。2015/12/28
ゆうきなかもと
6
天から降って湧いてくる何かを形にするのが、アランの考える芸術家なんだと思った。言い換えれば、時代、環境、テクノロジーと個人の持っている資質が、ぶつかり合って、必然的に、ある芸術作品が生まれると言うこと。特に印象的だったのは、祭りを芸術の1ジャンルとして語っているところ。アランは独自に体系的に個々の芸術を把握していることが、「芸術の体系」と本書を読めばわかる。芸術とはなんぞやを考えたい人には多いに手がかりになると思う。2023/07/12
-
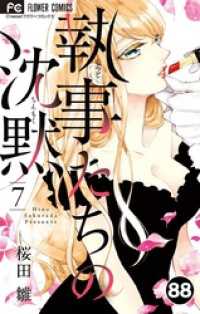
- 電子書籍
- 執事たちの沈黙【タテ読み】(88) フ…
-

- 電子書籍
- 雇われ悪役令嬢は国外追放をご所望です!…
-
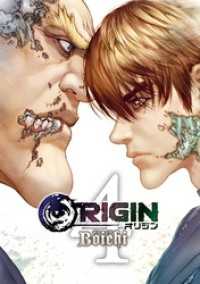
- 電子書籍
- ORIGIN(4)
-

- 電子書籍
- 愛は序曲に始まって ハーレクイン
-

- 電子書籍
- 世界のなかの日清韓関係史 交隣と属国、…




