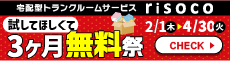- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
人間の生命現象である、脳・神経系の働き、骨格系と筋肉、呼吸器、循環器、消化、排泄、生殖の仕組み、さらには、それらを行っている膜の働き、物質輸送、シナプス伝送、電位の発生、興奮、制御など、人体のあらゆる生理の仕組みと働きを扱う科学分野を「生理学」と言います。上巻は「動物機能編」とし、感覚器、神経、運動器をカバーします。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ひめありす@灯れ松明の火
41
仕事の本。職業柄知ってなくちゃいけない事が多いのだけど、ちゃんと勉強した事がなかったので。高校の生物の教科書くらいの平易な書き方なので読みやすい。アセチルコリンとか前頭前野とか大脳辺縁系とか昔習って言葉としては覚えて居た物が沢山出てきて『そうそう、そうだったね!』となりました。言語のウェルニッケ領域とブローカ領域とか舌の味蕾の位置とかはまっていたなあ。勉強していたはずなのに、何だかノスタルジックな気分に浸ってしまいました。肝心の勉強したかった部分は下巻の分野らしいので引き続き下巻も読んでいきたいと思います2016/09/16
anaggma
4
健康に興味を持つと、とどのつまり生理学に行きつく。キャンベル本を読む前の助走に。2018/07/12
gachin
2
著者は傑物/ 網膜や心筋には電気シナプスがある。平滑筋は引き延ばされると収縮するので自己組織的に律動する。神経支配はその修飾のみを行う。心筋の筋小胞体中はCaイオンが乏しく、長時間Caを取り込む必要がある。その為、脱分極の時間が長く、荷重賦活が起きない。筋を伸長していくと1a反射に抑制性1b反射が続くので、折り畳みナイフ反射が起きる。触圧,温冷,痛は自由神経終末で受容するが、皮膚からの深度で分別されてる。脊髄ショックの持続時間は下等動物ほど短い。REM睡眠時は骨格筋の活動が消失する。2022/05/04
アルカリオン
1
BookWalkerのPC用Readerで。何の気なしに27インチモニターでフルスクリーン表示してみたところ、本文は予想通り読みにくいのだが図表の箇所になると、ひとつの図表だけがフルスクリーンを占領してでかでかと表示されるようになり、大迫力!これはこれでありだな。2018/11/04
こうきち
1
なるほど。前半は、文章ヘタか?とおもったけど、内容はしっかりしてるぞ!筋肉関係は、しっかり勉強したいな。2017/12/27