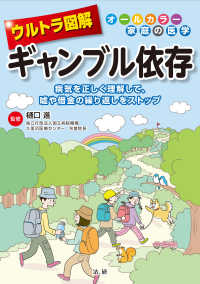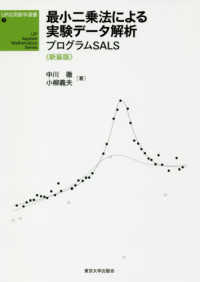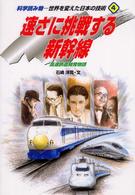内容説明
日本人にとって「電車」は、定刻どおりかつ安全な乗り物であるのが当然至極。しかし、日本の鉄道を支えているものはじつに膨大であり、どれ一つ欠けても、連携が崩れてダイヤはたちまち乱れる。本書では、一般の人が日ごろ意識せず、またあまり情報公開されることのない鉄道関連の4つのジャンル――「分岐器」「地下鉄トンネル」「窓ガラス」「パンタグラフ」にスポットを当て、その製造開発秘話や現場の苦闘を紹介。鉄道を日々「つくる」技術者たちの英知を知ることで、日本の新たな側面をかいま見る。
川辺謙一(かわべけんいち)
鉄道技術ライター。1970年三重県生まれ。東北大学工学部卒、東北大学大学院工学研究科修了。化学メーカーに入社、半導体材料などの開発に従事。2004年に独立し、雑誌・書籍に数多く寄稿。鉄道関連のさまざまな職場や当事者を取材・紹介したり、高度化した技術を一般向けに翻訳・解説している。近著に『鉄道のひみつ』(学研パブリッシング)、『図解・地下鉄の科学』(講談社)、『電車のしくみ』(ちくま新書)、『くらべる鉄道』(東京書籍)、『鐵路大比較』(台湾東販・中国語版)、『図解・新幹線運行のメカニズム』(講談社)がある。本書では図版も担当。
目次
第1章 日本最大の分岐器をつくる
第2章 地下鉄をつくる
第3章 電車の窓ガラスをつくる
第4章 電車のパンタグラフをつくる
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
33
今まで読んできた鉄道関連書籍の中でも異色の内容。しかも旅先の列車の中で読み始め、読了できたのが良かった。時速160㎞で走り抜けることのできる転轍機。部材の搬入から加工・組立・運搬までの全てが興味深い。転轍機(ポイント)を通過するたびに、在来線と新幹線の違いが列車に乗りながら実感できた。窓ガラスやパンタグラフもなかなかお目にかかれない話題だ。2016/02/21
mazda
17
パンダグラフ、分岐器(いわゆるポイント)など、普段電車に乗っていても気にしないところを詳細に書いてくれている本。鉄道の世界でも「ガラパゴス化」が起こっていて、パンタグラフのような部品でも規格が異なり、海外に輸出することが容易でないらしい。逆に言うと、それに守られて、これまで輸入品が入ってこなかった、ということでもある。毎日電車に何の心配もなく乗れるということは、こういうパーツの1つ1つが高い信頼性を持っているからである、と改めて感じた。2013/04/08
totssan
1
マニアックな4つの記事を結構詳細に記した鉄道本。1本あたりこれくらい記事量があるとうれしい。非常に参考になった。2019/11/20
Kentaro
1
ダイジェスト版からの要約 電車の窓ガラスに新たな価値を付け加える検討が行われている。その例が電子カーテンと情報提供機能である。電子カーテンは社内に入る光を電気的に調節し、窓ガラスをタッチパネル式にすることで乗客がタッチするだけで暗くなる場所を調節できる。外の景色も見ながら一部だけ暗くすることが出来そうだ。情報提供機能は窓ガラスそのものがスマートフォンやパソコンのディスプレイのようになる機能だ。降りる駅までの所要時間や乗換駅なども簡単に切り替えられる以上のことが出来るだろう。あとはコストと安全性だろうか。2018/05/30
rbyawa
1
d120、面白かった、そして正直ネタが細かかった。今まで何度も「シングルアーム」や「ビューゲル」という単語は聞いていて、なんとなくの性能のような部分は把握して聞いてはいたが、まとめて説明してくれていて嬉しかった。鉄道技術本を書いていて、難しいと言われることがあり、完全に題材を絞って語るという試みをしている。分岐器、地下トンネル、窓ガラスにパンタグラフを取り上げていて、基本的にそこから話題が広がらない。マニアの評価が微妙になるのもなんとなくわかる気はするがこの本は素人の知識量でも多分読めるんじゃないのかな。2013/08/23
-
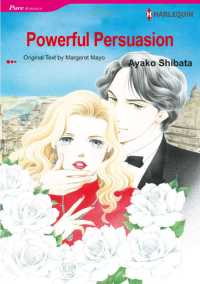
- 電子書籍
- Powerful Persuasion…