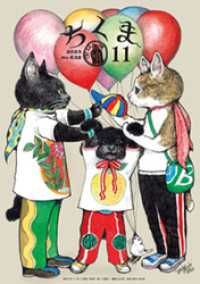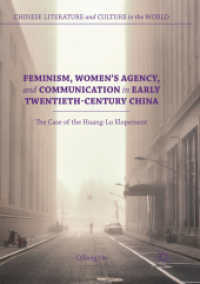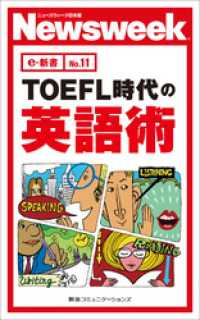- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
私たちは,ことばを通して世界を見たり,ものごとを考えたりする.では,異なる言語を話す日本人と外国人では,認識や思考のあり方は異なるのだろうか.「前・後・左・右」のない言語の位置表現,ことばの獲得が子どもの思考に与える影響など,興味深い調査・実験の成果をふんだんに紹介しながら,認知心理学の立場から語る.(カラー口絵2頁)
目次
目 次
序 章 ことばから見る世界──言語と思考
第一章 言語は世界を切り分ける──その多様性
色の名前
モノの名前
人の動きを表す
モノを移動する
モノの場所を言う
ぴったりフィットか、ゆるゆるか
数の名前のつけ方
第二章 言語が異なれば、認識も異なるか
言語決定論、あるいはウォーフ仮説
名前の区別がなくても色は区別できるか
モノと物質
助数詞とモノの認識
文法のジェンダーと動物の性
右・左を使うと世界が逆転する
時間の認識
ウォーフ仮説は正しいか
第三章 言語の普遍性を探る
言語の普遍性
モノの名前のつけ方の普遍性
色の名前のつけ方の普遍性
動作の名前のつけ方の普遍性
普遍性と多様性、どちらが大きいか
第四章 子どもの思考はどう発達するか──ことばを学ぶなかで
言語がつくるカテゴリー
モノの名前を覚えると何が変わるのか
数の認識
ことばはモノ同士の関係の見方を変える
言語が人の認識にもたらすもの
第五章 ことばは認識にどう影響するか
言語情報は記憶を変える
言語が出来事の見方を変える
色の認識とことば
言語を介さない認識は可能か
終 章 言語と思考──その関わり方の解明へ
結局、異なる言語の話者はわかりあえるのか
認識の違いを理解することの大事さ
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
おたま
けんとまん1007
1959のコールマン
Nobu A