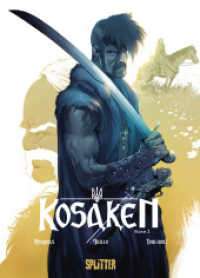内容説明
本書は、人間の心理には無意識の抑圧と抵抗という複雑なメカニズムが存在し、ノイローゼの原因にはリビドーが深く関係していると唱えて、精神現象の解明に偉大な貢献をしたフロイト理論を理解するための絶好の手引きである。講義録である「錯誤行為」「夢」「神経症総論」の三部に続いて、修正補足を目的に書かれた「精神分析入門(続)」を併せて収録する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
113
下巻は『神経症総論』の続きに加えて修正補足を目的に書かれた『精神分析入門(続)』を併録。専門性と共にアプローチの独自性も飛躍するのでより難解に。無意識の抑圧と抵抗が形成する複雑なコンプレックスをノイローゼの原因とする著者。意識は心的構造における氷山の一角でしかない。自我・超自我・エスといった領域的区分、無意識・前意識・意識という作用的区分、更には幼児性欲論など説明の手法も内容も大いにスパイシーだ。臨床医としての人道主義な表情を見せる一方で、キリスト教やマルクス主義を痛烈に批判したりと当時の時代性も窺える。2018/02/04
syaori
62
下巻では神経症の症状は無意識下に蠢くリビドーが意識の検閲機能に拒否されたその満足の代理だと語られます。このリビドーと、外界の現実に沿ってそれを検閲する自我欲動との葛藤が神経症の病因で、しかし正常者にも起きていることが夢の症例から示されます。この葛藤は後に道徳の権化の超自我、自我、無意識的なエスとされ、外界・超自我・エスを調和しようと苦心する自我という構図になりますが、どちらにしても人は他者との関係でも自身の心の内でも尽きせぬ葛藤の中で生きているのだと思われて、生を苦しくも豊かにもする欲動の力を思いました。2023/06/09
加納恭史
20
ベルクソンはフロイトの影響を受けた。「道徳と宗教の二源泉」で動的宗教(キリスト教やイスラム教など)は神秘主義や神秘体験を認めているのはフロイトと同様だな。そこでフロイトの精神分析(下)を読んでみる。かなり前に夢判断も読をだが、難解だった。ただ夢見る本人の願望の現れだったな。今回の精神分析はまた一歩進んだ形だな、更にその続きがある。意識には自我(私)と超自我(上の私)と前意識と無意識がある。記憶が蘇る前意識と無意識は記憶が蘇らないで、その中にエスがある。原始的な私かな、また情動らしい。超自我も無意識にある。2023/10/19
たかしくん。
20
とりあえず、前半28章までにて読了とします(「続」は、いつか又!)。上巻からの、リビドー論は更に深堀られ、まずは、幼児期の倒錯したリビドーから始まります。その「前性器」体制の特徴は、サディズムと肛門愛への部分欲望。その時期のサディズムが高じたものが、カラマーゾフの父親殺しとフロイトは言いたいのでしょうね。そして、随所に取り上げられる近親姦。LGBTを積極的に寛容する現代社会で、これを差別することが偏見だと言われかねない時代が来るかも…。なんて、うすら寒い「白日夢」が頭をよぎりまして。。2019/06/08
ヨッフム
19
上巻に続いて、神経症総論、とりわけ不安についての講義が大変面白く、対象のあるものを恐怖、そして対象の喪失したものを不安と呼び、その根元には、出産体験における心的外傷が絡んでいるのではないか、という発想が飛び抜けて面白かった。科学万能主義の時代に影響はうけつつも、決して実証に拘らない姿勢が見受けられるのが、フロイトが思想家と呼ばれている由縁なのかな。それにしても、超自我とエスの板挟みになって、精神の全責任を取らされる、自我の孤独さよ。生き延びるために心を病む、という涙ぐましい努力を思うと、ぐっときます。2015/02/04