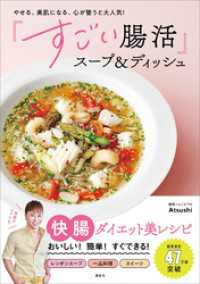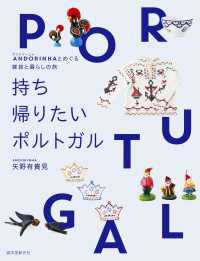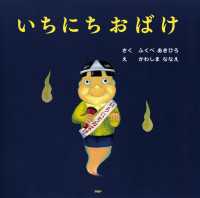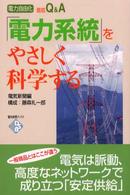内容説明
ついに出た、「落語論」の新機軸(イノベーション)!!
ユニークな活動で注目される談志の孫弟子が、落語の面白さをイチからお教えします。
「立川談志の『現代落語論』からちょうど半世紀というこの節目に、あの頃の家元と同じく30歳前後の自分が『現在落語論』というタイトルでこの本を書く。
16歳で落語の門を叩き、すぐに頭角を現し、27歳で真打となり、メディアでも売れに売れて落語界に確固たる地位を築いていた当時の談志と、26歳で落語の門を叩き、二ツ目になったばかりの自分とを比べることなどできるわけがない。
ただ、現在を生きる落語家であるぼくには、これまでの先輩方がそうしてこられたように、受け継がれてきた落語の面白さを、色あせないようにたえず磨きつづけていく責任があるのだ」
――「まえがき」より
<目次>
●第一章 落語とはどういうものか
何にもないから何でもある
落語の二面性── 伝統性と大衆性
古典落語と新作落語
マクラは何のためにあるのか
●第二章 落語は何ができるのか
省略の美学
使い勝手のよさ
古典落語を検討する
●第三章 落語と向き合う
志の輔の新作落語
談笑の改作落語
擬古典という手法
ギミックについて
●第四章 落語家の現在
吉笑前夜
「面白いこと」への道
落語界の抱える二つのリスク
落語の未来のために
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
34
題名をあやかった大師匠の本ほどに大上段に構えることはないものの、自身の落語と絡めつつ、古典とは、伝統とは、噺家とは、笑いとはという落語を語る上で必ず突き当たる設問に、現役の二ツ目の視点で応えている。著者を知っているか、高座を聴いたか、好きか嫌いかで評が分かれるところ(ポジティブとて、必ずしも肯定な訳では無い)。公平を期して知らず知らず評価が偏るのは、好事家の原罪。立川流かつ談笑師の弟子というエクスキューズあったからこその書籍での発信。協会に属するような噺家には、無用にして不要。寄席の空気は不立文字な故に。2016/01/17
zirou1984
27
立川談志の孫弟子であり自分と同世代でもある著者による落語論。執筆時点で二ツ目というのもあり迷いや自信の無さも顔を出すが、古典の系譜を踏まえながらも落語の可能性を探求しようとする姿勢は、結果的に落語入門としても楽しめる内容となっている。落語の可能性として衣装や下半身を省略したからこそ「何にもないから何でもできる」武器を持っているのだという指摘は納得であり、伝統と現代の落とし所としての改作落語の可能性については興味深い。それにしても師匠・談笑による芝浜の改作落語『シャブ浜』は時事ネタ的に気になり過ぎてヤバい。2016/11/28
茉莉花
25
落語について全く知らなかったのですが本書を読んで落語に興味を持ちました!ひとことで云うと落語って奥が深い!座布団の上で正座するのも意味があるし、落語は「何にもないからなんでもある」のです!何もないとこから荒唐無稽な話が突然出てきてそれが自然と具現化し、更には時、場所の転換が自由自在に行われる。ただ、笑いだけではなく感動を与えたりメッセージ性が宿ってたりする。本書にあった「舌打ち」と「粗粗茶」のネタは面白かった!今度、youtubeで落語を見てみたいわ!と思いました(≧∇≦)2016/05/22
Nazolove
24
いよいよ二つ目にまで本が書けるとは、やはり立川流は物書きの才能がないと入れないのではないか、なんて思った。 正直談笑さんのネタ面白いけどちょっと品がないよねなんて思っていたがこれからは好き嫌いせず是非聞いていこう。 この人の弟子入りしてからの日記?みたいなのを是非読んでみたいなと思った。 なにげにちょっと月亭方正さんをディスってるんじゃないかな、なんて思ってしまった。 この人くらいの若い人がもっと落語を好きになっていけばいいのではないかと思う。2017/04/25
遊々亭おさる
17
「自分が落語家であることの爪痕を世間に残してやる」尖りつつもどこか気弱な若手落語家が飲み屋で後輩相手に野心と落語の技術論、そして未来への危機意識を熱く語るといった風情の一冊。お笑いが好き、夢を追いかける熱さが好きな方におすすめ。伝統芸能と大衆芸能、どちらに振り切れても落語の面白さは消滅する。『伝統を現代に』の談志イズムを継承し、漫才やコントでは表現出来ない落語ならではの面白さを追求しようと暗中模索する姿に若いっていいなと少し嫉妬を覚える読後感。芸能の未来のためにNHKさん辺りで落語版M1の開催なんてどう?2016/10/28