- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
いかに生き(生計)、身を立て(身計)、家庭を築き(家計)、歳を重ね(老計)、そして死を迎えるか(死計)――。この言葉は遠く南宗の時代に、見識ある官吏として多くの人たちに深く慕われた朱新仲の悠々たる人生訓である。本書は人間学の権威として世人の敬愛を集めた著者が、この教訓にヒントを得ながら、深い究明と実践により、独特の論法をもって唱えた『人生の五計』を、いかに現代に活かすかについて語り明かした講話録である。「日用心法」=「日々作用する、働く、その心掛けの法則」「朝こそすべて」=「本当にその時刻において、われわれのすべてが解決される」「師恩友益」=「”いい師””いい友”に巡り会わなければ、いかに天稟に恵まれていても独力では難しい」「良縁と悪縁」=「人生のことはすべて縁である」など、今日という日の重みを大切にし、真の幸福をつかむための智恵を解説している。相手の心を高め、善く生きるための深遠な教え。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Yuma Usui
11
「生計」「身計」「家計」「老計」「死計」といった、五つの章で構成された一冊。例えば「生計」では、「論理」の抽象的な欠点から感情的・精神的に納得ができる「情理」が最も大事だと説いており、それが自然に近づくと「真理」、具体性を持つと「道理」となるという説明は腑に落ちた。また、コンピュータと人との違いを述べた箇所ではシンギュラリティについても触れており(本書ではシンギュラー・ポイント)、昭和の講話録と思えないほど時代の先を見据えた内容だと思う。過去や歴史に学ぶことの大切さを感じた。2018/03/10
Nobuchika Hotta
8
戦後、機械文明が発達し、生活様式が便利になり、戦前の思想が全否定され、社会主義的な思想が蔓延するなか、東洋哲学や日本古来の良き倫理観を日常生活のなかでどのように取り入れて行ったら良いかを具体的に説く。朝早起きし、真向法という下半身のストレッチを行い、読書を習慣とする。暴飲暴食を謹み、友人、家族に穏やかな態度で接し、正しい日本語を使う。「参る」という言葉に愛するという意味と尊敬の意味が含まれていて、スポーツで負けた相手に「参りました」という言葉をかけるのは日本人だけだ、との趣旨の記述に深く心を打たれました。2011/09/23
だんぶる
7
人には敬愛か必要 幼き子 成長段階にある子、成長してほしいと認めている人 に対しては敬して向かい合う必要がある。 自分の相手に対して成長してほしいという気持ちを表し それを受ける者はしっかり受け止め 恥ずかしがらず 茶化すことなく 自らの成長に向けて努力べきである。 愛は動物にも備わっているものでありこちらも大事であるが、敬が足りていない、満たされていないのではないか。不足しているのではないか? 死を畏れる中から畏れない理由を生み出す よく考えて行動して社会がより良くなるために生きていこう。2020/08/22
大先生
7
生計、身計、家計、老計、死計という人生の五計が曖昧なままであれば文明社会は没落してしまう。この本では「五計」の片鱗を覗いたに過ぎないとのことですが、大いに学ぶところがありました。身計の章では、安岡正篤先生の学生憲章や教師憲章が掲載されていますが、格調高く素晴らしい内容だと思います。例えば教師憲章第二章「子弟が将来いかなる地位に就いても人から信用され、いかなる仕事に当たっても容易に習熟する用意のできておる、そういう人間を造ることが教育の主眼である。」これは、ケンブリッジの教育方針でもあるようです。2020/05/25
Willie the Wildcat
5
安岡氏の著名な五計「生計、身計、家計、老計、死計」。自身の人生への姿勢を問い直す一冊。時代を超えた不変の真理。2009/11/29
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢はラスボスの密偵として学食で働…
-

- 電子書籍
- 学園天国(分冊版) 【第48話】 ぶん…
-

- 電子書籍
- 人は、なぜさみしさに苦しむのか?
-
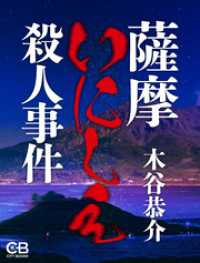
- 電子書籍
- 薩摩いにしえ殺人事件
-
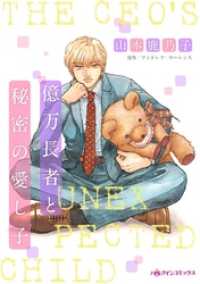
- 電子書籍
- 億万長者と秘密の愛し子【分冊】 12巻…




