- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
フロイト=ラカンを超えてヴァージョン・アップ。「私」とはなにか。それはいかに作動し、「経験」を作り出し、自己を変容させるのか。「システム」をキーワードに、21世紀における新たな精神分析の構築を試みる。(講談社選書メチエ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
10
惨めな気分にさせる患者相手の治療で自分の感情とか見た夢をもとに患者の自己を解釈していた過去への反省を通じて、絶えざる自己形成としての精神分析を提示した本。オートポイエーシス理論を援用しラカンでも対象関係論でも自我心理学でもない新境地を開くという目的は、著者が危惧するように類書と同じく、自己システムとか社会システムとかコミュニケーションシステムとか語尾にシステム語を付けて言い換えただけの懸念が残る。しかし患者のみならず精神分析家も自己形成を続けていく営みなら、最初から完成形が到来しないのも当然とは言える。2019/08/23
くろねこ
1
自己システムとして、「私」を理解するあり方はわかりやすく、そこから病理、治療へと視点を進めていく。途中やや付いて行ききれないところもありますが、頭が整理される感じです。どのように「私」を「人間」を理解するか、理論を組み上げるか、現代を生き、精神分析的な経験を生きる中での著書のあり方に感銘を受け。第二章の臨床と絡むあたりはぐいぐいと読めます。2019/07/31
engawa
0
著者は、人間の自己を、様々システムの複合体と考える。特に、興味深かったのは、人間の記憶システムには、言語習得以前の幼児型と、言語中心の成人型があり、通常作動しない幼児型記憶が、精神的外傷によって作動するということ。実際は、常に作動しているんではないか? エディプス的ではない変化し続ける自己も、今、国も法律も機能不全に陥っている状況で、興味深い。多分、近代は終わりつつあるのだから。ところで、自己は様々なシステムの複合体として、死後も残る部分はあるのでしょうか? 言語システム中心の記憶は残らないのでは?2011/07/16
yoyogi kazuo
0
前半の理論的な部分は難しかったが精神分析家としての臨床経験に基づく記述、特に後半部分を興味深く読んだ。2023/01/28
-
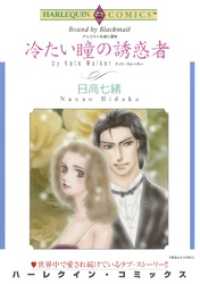
- 電子書籍
- 冷たい瞳の誘惑者【分冊】 4巻 ハーレ…
-
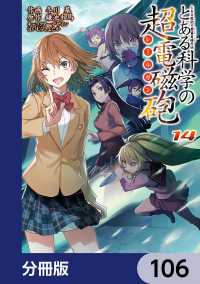
- 電子書籍
- とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の…
-

- 電子書籍
- レッスルキャンパスvol.1 レッスル…
-
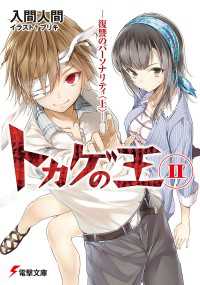
- 電子書籍
- トカゲの王II ―復讐のパーソナリティ…
-
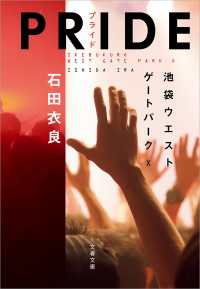
- 電子書籍
- PRIDE - 池袋ウエストゲートパー…




