内容説明
「救える命」を見殺しにする医療権力の正体とは――。
日経連載小説『禁断のスカルペル』のモデルにもなった“医療界のタブー”に迫った本格的ノンフィクション。
1000例を超える手術実績、海外からも高く評価される修復腎移植(下記※)の先駆的な技術を持ちながら、不当なバッシングにさらされ保険医登録抹消寸前まで追い込まれた万波誠医師ら「瀬戸内グループ」の移植医療の真実の姿を、10年にわたる取材で詳細に明かす。
万波つぶしに狂奔し移植の機会を奪ったとして患者団に訴えられた日本移植学会幹部への取材も収録。 現在31万人を超え、年々1万人増加している透析患者(1人年間500万円を国が負担)による財政圧迫の問題、「2兆円市場」となった人工透析にからむ利権問題にもメスを入れる。
真に患者のQOL(生活の質)を優先する医療として世界的に評価される修復腎移植を世に問うとともに、日本の医学界のモラルと体質を厳しく追及する。
※=「修復腎移植」とは、ドナー(臓器提供者)から摘出されたガンなどの病気腎を修復し、レシピエント(移植を受けいれる患者)に移植するもの。「病気腎移植」と呼ばれることもある。宇和島徳洲会病院の万波誠医師ら「瀬戸内グループ」が先駆的に取り組み、実績を上げてきた。だが、日本移植学会が猛烈に反対し、厚労省も禁止の通達を出すに至った。世界的には安全性が確認されつつあり、腎臓移植の新たな潮流となっている。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Teruhiro Komatsu
1
母ちゃんの従兄弟が瀬戸内グループの一人、西光雄医師なんですけど、そういう贔屓目を抜きにしても、つくづく巨大市場となった人口透析に絡む巨大利権によって修復腎移植の先進医療認可への道が阻まれているのだという事実を思い知らされましたです。以下引用。【心停止、脳死による移植は減る一方、その上、修復腎移植は原則禁止に追い込まれてしまった。海外で移植を受けたレシピエントには診療拒否が待っている。透析治療にもやがて限界がやってくる。これでは腎不全患者に「座して死を待て」といっているのに等しいのではないか】2015/08/11
Hiroo Shimoda
0
日経朝刊の小説で興味を持って。ハイリスクハイリターンな医療をどう考えるか。自己責任ならいいよね、と考えたくなるが、移植を目的とした不必要な摘出手術への誘導が産まれるリスクはあり、そう単純ではない。難しい。2015/08/28
sab
0
記者魂を感じるノンフィクション本だった。事件の経過を小説化したものを先日読んだが、この事件の流れ自体がかなり面白いものである。加えて現場VS権威の構図、そして権威の方には利権が絡むというお決まりのパターンを地で行く構図。移植学会(敵側)でも著者からの質問状に唯一回答のあったと言う大島医師の話は、権威側の事情を斟酌すべきものではあった。しかし最終的に未だこの医療が正式に認められておらず、裁判でも原告側の主張が認められていない。反対側の主張もこの本の中で紹介されているものしか読んでいない。もう少し掘り下げたい2020/01/28
かさい
0
日本の移植医療が10年遅れたと言われる修復移植腎問題についての本。透析での10年生存率が40%近くで、安全性についても生体腎移植と有意差を示さないこの技術を、なぜ推奨せずに潰しにいくのか。透析医療に携わる大手製薬会社と移植学会との癒着などが指摘されていた。すごい分かりやすいし、臓器移植への考え方も改まると思う。おすすめ。 ただ、日本は医療訴訟が増えてるからなかなか移植が流行らないんだろうなとも思う。医師だけでなく、国民の意識を変える必要もあるんじゃないかな。2019/11/02
-

- 電子書籍
- 身代わりの花嫁はヤンデレ領主に囚われる…
-

- 電子書籍
- バイオハザード デスアイランド【タテス…
-

- 電子書籍
- 靴下の妖怪【タテヨミ】第57話 pic…
-

- 電子書籍
- ツチノコと潮風 5話 ebookjap…
-
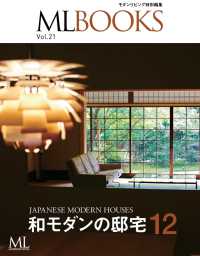
- 電子書籍
- ML BOOKSシリーズ 21 和モダ…




