内容説明
養殖鯛より天然鯛のほうが美味しいように、家畜肉よりジビエのほうが美味しい。日本人と肉食の関係は、まだどこかよそよそしい。「高い」「クサい」と敬遠されてきたジビエの魅力を伝えるべくフレンチ料理家の狩猟女子が立ち上がった――。日本人には「ジビエは臭いし硬い」と食わず嫌いの人が多い。しかし、初めて食べた人は、その美味しさに驚愕するという。「アナグマの肉はフルーツの味がする」など、きちんと処理された狩猟肉は臭くないのだ。日本での狩猟は、農作物の害獣駆除として行政がハンターを雇う駆除が主で、行政の許可を受けた施設でしか解体加工、流通できないため、年間10万頭が廃棄されている。害獣駆除、食糧自給率アップ、美味しくてヘルシーといったメリットがあるのに、実に憂慮すべきことだと著者は考える。フランスでの料理家修業時代に欧州の食肉文化に触れ、日本の食肉文化の浅さを感じた著者は、処理施設のある福岡を拠点にした猟師グループ「Tracks」に加わり、“ハンターガール”として捕獲した狩猟肉の料理をするほか、福岡産ジビエの販路を広げる活動をしつつ、狩猟アドバイザーとして全国を飛び回る。ハンターガールならではの「狩猟ファッション」にもこだわる。本書では、ジビエの本場で修業をした女性シェフが荒々しい動物たちと向き合い、日本にジビエ文化を広げるべく奮闘する姿、狩りを楽しみ、味わい、自然と共生する喜びを語り尽くす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
to boy
30
料理家の著者が、「どこまでが『命』で、どこからが『食べ物』だろう」と疑問を抱き、ジビエ料理に出会う中、山に入って獲物をとるところから経験してみようと試みた本。猟銃免許まで取得し、仲間たちと猪やアナグマを仕留め料理をしながら疑問への回答を見つけていく。料理家だけあってそのメニューを読むだけでよだれが出てきそう。なかなか面白い一冊。2019/02/14
しーふぉ
22
熊谷達也のまたぎ小説を読んでから猟に興味を持った。若い女性の料理家が食べることを考えて、実際に狩猟免許の取得や猟に同行し解体を行ったりをしたことを書いています。罠を仕掛け猪が掛かると鉄パイプで眉間を打ち気絶させてからナイフで動脈を切る…毎日続けるのは精神の消耗が甚だしいのが良くわかる。生々しい写真も少しあるので苦手な人は注意!2017/08/20
けんとまん1007
16
ジビエ・・たまに聞く言葉になった。命をいただく。その重さを感じることこそ、大切なのだと思う。そのための奮闘ぶりが、気持ちの変化も含め、伝わってくる。肉を見るのも辛くなってくるというあたりが、何となくではあるが、わかるような気がする。今の時代だからこそ、命の重さ、それを奪う場面を隠してはいけないのではないかと思う。「生き物」と「食べもの」という言葉が印象に残る。2015/09/13
たくのみ
14
「食べること」の先にあった疑問「食べることって生き物を殺すことじゃないの?」「どうしたら、いただいた命につながっていけるのだろう」の答えはジビエを自分で捌くことにあった。「狩猟で獲った食材」を意味するフランス語・ジビエを実践するために狩猟の免許をとって狩猟生活を実践していく。まさに女性版「山賊ダイアリー」イノシシは臭い、タヌキは食えない、すべて思い込み。そして、害獣を流通に乗せられないのは「解体処理施設」が圧倒的に不足しているから。食の意外な話題も豊富です。労作「4種の禽獣のラグー」かなり食べたいです。2015/04/17
あび
8
なんだかどうしても、ファッション的な目的で狩猟を行なっているように思ってしまう。料理家なのでレシピの話題が表立って出てくるのは仕方がないとしても、どうしても1つのキャラクター付けのためにやっているように感じる。そもそも自分で狩って食べることが重要で、すでにパック詰めされた肉を食べることでは命の尊さが学べないという考えも、押し付けがましいというか。。なんだかずっと変なモヤモヤが続きながら読み終えた。2017/05/28
-

- 電子書籍
- 処刑寸前の悪役令嬢なので、死刑執行人(…
-

- 電子書籍
- 婚約者と三人の元カレ 23 COMIC…
-
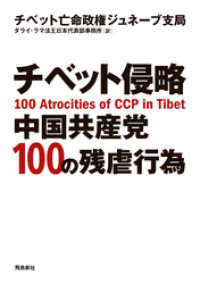
- 電子書籍
- チベット侵略 中国共産党100の残虐行為
-
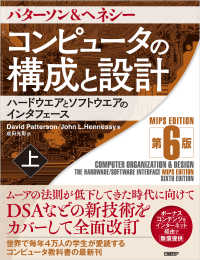
- 電子書籍
- コンピュータの構成と設計 MIPS E…
-
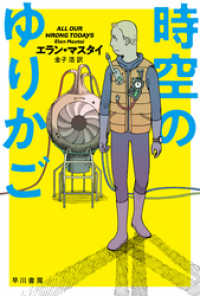
- 電子書籍
- 時空のゆりかご ハヤカワ文庫SF




