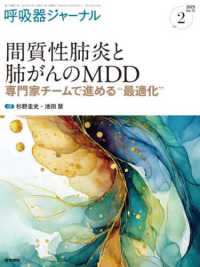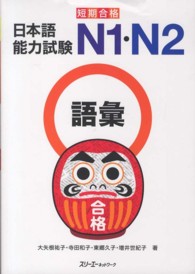内容説明
身体を見つめてきた解剖学者と世界を駆けまわる建築家が、現代日本の大問題、「死に方」について考える。
中高年男性の自殺率が世界でもトップレベルになった日本。
「死」が徹底的に排除された都市に住み、「死」について考えなくなった私たちは、
どのように「死」と向き合い、「その日」を迎えればいいのだろうか?
解剖学者と建築家という異色のコンビが、鴨長明の『方丈記』や、東京の歌舞伎座、
そして同じ学校で受けたキリスト教式の教育などをヒントに、ときにユーモアを交えながら、縦横無尽に語り合う。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あちゃくん
84
養老さんと隈さんの対談の第二弾です。今回は前回より隈さんの魅力というか考えがより感じられました。新しい歌舞伎座の話と鉄道は「時間」を引き受ける仕事だという話が面白かったです。2015/11/08
金吾
30
どう死ぬべきかという話としてはあまり参考にならなかったですが、方丈記の話は面白かったです。2023/08/22
1.3manen
26
隈教授:死が想定されていないマンションに、死が想定される老人がいっぱいいる(55頁)。限界団地の現実か。日本で一番自殺するのは中年男性(80頁~)。40~60代(隈教授)。まだまだこのリスクから解放されることはない 当事者である。養老名誉教授:御嶽噴火で登山規制なら90度の議論で家から一歩も出られなくなる(112頁)。 隈教授:1889年東京日日新聞主筆福地桜痴(おうち)が初代歌舞伎座を実現、彼のおかげで歌舞伎が生き残っ た(147頁)。 2015/03/10
せろり
9
俺は死んでも俺は困らねぇ! 相変わらず養老先生カッコいい。 人は自分の死は考えても仕方ないんです。2015/08/23
sun
7
「死」について、より広い範囲の鼎談。隈さんは建築を作りまわっていて、現実に動いており、その裏側や思想を語ってくれる。養老さんはここでは他の本の「語り」の元となる非常に広い教養を示してくれる。それぞれが「動いている」と感じられる。「生」きていることは、料理を作ったり。草むしりをしたり、「動いていること」、だと感じさせる。まさに「生」物、それこそ「動的平衡」だ。2016/10/08
-
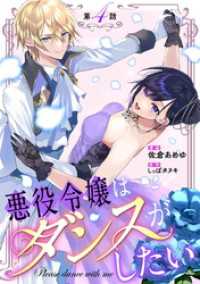
- 電子書籍
- 悪役令嬢はダンスがしたい 第4話【単話…