- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
アフリカで生まれ,二足歩行を始めた人類は,空いた手で荷物を運び,世界にちらばっていった.この〈運ぶ〉という能力こそが,ヒトをヒトたらしめたのではないか?アフリカ,ヨーロッパ,東アジアの三つの地点を比較対照し,〈運ぶ〉文化の展開と身体との関係を探る.人類学に新たな光を当てる冒険の書.
目次
目 次
1 なぜ、「運ぶヒト」か?
ヒトはアフリカで生まれ、世界にひろがった
アフリカを出たとき、どうやってものを運んだのだろう?
直立二足歩行が、「運ぶ」ことを可能にした
直立二足歩行のはじまりは?
頭蓋骨から推定できる二足歩行
だが、そもそもヒトのはじまりは?
これもヒトだけの特徴「二重分節言語」
では、ホモ・ポルターンスを研究する方法は?
2 文化の三角測量
文化を比較する二つの方法
轆轤を逆にまわす
日本での琵琶の普及
風が吹けば桶屋が儲かる
「はたらく」よろこび? それとも経済外的強制?
労働をねぎらい、励ます言葉が豊かなモシ社会
自己主張のつよさ
市で活き活きとするヨメたち
地縁組織の弱さ
人間と道具の関係で比較すると
アフリカ式溶鉱炉
夏雨型農耕と冬雨型農耕
前屈したままでの除草の方がラク?
冬雨型のフランスではアザミ除去に一苦労
文化の比較から、「身体技法」の比較へ
3 「身体技法」としての運び方
身体と文化
身体技法の集合としての「おこない」
モノとのかかわりでの身体技法
「運ぶ文化」にとっての生態学と働態学
二重分節言語の条件
運ぶ行為における、身体と道具
西アフリカ黒人の身体特徴
育児法などとの関連
運搬法にみる三つの指向性
前頭帯運搬の系譜は
黒人、白人、黄人にみる運搬具の共通点と差違
4 「技術文化」と運搬法
技術文化の指向性
ヒトと道具──三つのモデル
道具をまたがない日本の職人
前頭帯と棒運搬をめぐる文化
石器文化の西と東、竹の文化は?
「朸」が提起する問題
棒でかつぐ運搬の日本での異常な発達
中国でも多様だった棒運搬
三文化における「履き物」
背負い運搬における重心の高低
人力以外の動力活用への指向
日本の川船輸送との比較で
蒸気機関以後
5 「運ぶヒト」のゆくえ
はじめどうやってモノを運んだか、再び
頭上運搬の移り変わり
より効率のよい運び方へ
現代日本における身体技法
「ナンバ歩き」
「グローバル化」とは?
グローバル化のはじまり
進歩をめぐる楽観から、先の見えない悲観へ
エスニックとグローバルのあいだ
モノ運びの仮想パレード
メキシコの少年らのグループ
フランスのグループ
いま、アフリカでは
「運ぶヒト」の原点に帰って
参考文献
図版出典一覧
-
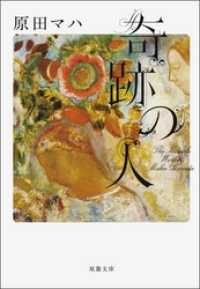
- 電子書籍
- 奇跡の人 The Miracle Wo…





