- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
織田信長の上洛から二〇年、豊臣秀吉により天下は統一された。集権化や実力主義を推進した信長と秀吉の政策はまさに「革命」であり、他の戦国武将と一線を画していたのである。本書はさらに、足利と織田、そして織田と豊臣の各政権が併存したことを指摘しつつ、軍事革命にともなうスペイン・ポルトガルの東アジア進出といった世界史的視野からも戦国日本を捉え直す。旧来のイメージを大胆に覆し、「革命」の本質に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tomoichi
16
漫画とは言え歴史フィクションを続けて読んでいると、まともな研究が知りたくて購入。結論としては信長と秀吉は天才ってこと(笑)家康?だれ? 信長の勢力拡大と足利幕府の終焉についてこれも一つの学説かもしれないが論理的で納得のいくものでした。著者の他の本も読もうかな。日本史update続く。2021/12/28
Porco
15
信長は本当はどこが革命的だったのか。室町幕府の終わりから豊臣政権の確立までの推移は、どう捉えるべきか。私の持っていた知識はことごとく覆されました。2022/12/27
浅香山三郎
10
久しぶりに藤田達生氏の著書を読む。信長や秀吉の「革命」の中身を再検討し、また著者の持論である鞆幕府論(安土幕府との対抗関係)に接続させる。流通を支配し、経済基盤がしつかりした環伊勢海政権としての織田政権、天下人の代官化する家臣=鉢植大名の制度化(これを支える理念としての預地思想)など、織豊期の政治のあり方をうまく位置づけてゆく。藤木久志氏の議論(豊臣平和令)を批判的に検討し、法令ではなく預地思想といふイデオロギーの影響を説く点に著者の議論の特色がある。これはこれで興味深いが、仮説に留まるだらう。2024/11/15
skunk_c
9
最近この時代について学びながら感じていた、足利義昭から織田信長に政権が移行した時期のことや、本能寺の変から羽柴秀吉が実権を握るまでの時期について、かなり説得力のある説明だ。特に義昭下向後も将軍としての役割を果たしており、二重政権だったとする説明は腑に落ちた。一方信長については、従来の天下への野心が強かったという説に近く、このあたりをどう捉えるかは考えどころ。信長、秀吉が預治思想により、大名を「鉢植」のように能力に応じて地方に配置する制度を確立(完成は徳川家康か)したあたりに革命をみるという説は面白かった。2015/09/22
ZEPPELIN
8
足利義昭に拘りすぎていて、序盤から胃液が出てくる。京に進出した信長と、京から追放された義昭。最高の権威である帝が京にいる以上、国の中央は京であり、西国に飛ばされた義昭が信長と同等の存在であったとは到底思えない。また、自説を強調するための論文や研究の取捨選択も都合良すぎで、「自分の見解は面白い!他人は古い!」という自己主張も強く、かなり鼻に付く。現在ならともかく、この時代に対する研究が京近辺に集中するのは当たり前ではないか。典型的なタイトル負けの本2014/07/21
-

- 電子書籍
- さようなら、エデン。【マイクロ】(31…
-
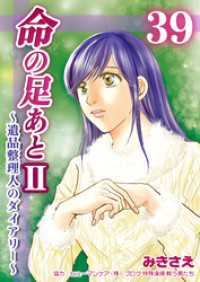
- 電子書籍
- 命の足あとⅡ~遺品整理人のダイアリー~…
-
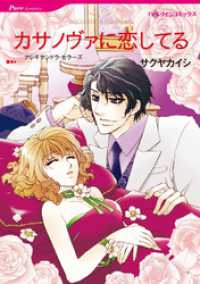
- 電子書籍
- カサノヴァに恋してる【分冊】 11巻 …
-

- 電子書籍
- 衣笠くんの×××をやめたい! 分冊版(…
-

- 電子書籍
- うめともものふつうの暮らし ストーリア…




