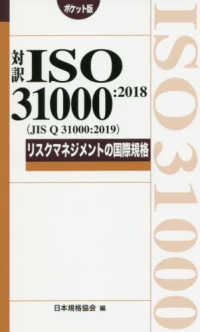内容説明
世界にはなぜ豊かな国と貧しい国が存在するのか?
『銃・病原菌・鉄』のジャレド・ダイアモンド、ノーベル経済学賞の歴代受賞者が絶賛する全米ベストセラー!
上記の問いに答える鍵は、地理でも、気候でも、文化でも、あるいは為政者の無知でもない。問題なのは政治・経済上の「制度」なのだ。
ジョン・ベイツ・クラーク賞を受賞したMIT教授のダロン・アセモグルと、気鋭のハーバード大学教授ジェイムズ・A・ロビンソンが、15年に及ぶ共同研究の成果をもとに国家の盛衰を決定づけるメカニズムに迫る。本書から明らかとなるのは――
○メキシコとアメリカの国境で接する2つのノガレス、韓国と北朝鮮、ボツワナとジンバブエ――これほど近いのに発展の度合いに極端な差があるのはなぜなのか?
○現在の中国はこのまま高度成長を続け、欧米や日本を圧倒するのか?
○数十億人の人々を貧困の連鎖から脱出させる有効な方法はあるのか? etc.
古代ローマから、マヤの都市国家、中世ヴェネツィア、名誉革命期のイングランド、幕末・明治期の日本、ソ連、ラテンアメリカとアフリカ諸国まで、広範な事例から見えてくる繁栄と衰退を左右する最重要因子とは? 21世紀の世界を理解する上で必読の新古典、待望の邦訳。
目次
第1章 こんなに近いのに、こんなに違う
第2章 役に立たない理論
第3章 繁栄と貧困の形成過程
第4章 小さな相違と決定的な岐路―歴史の重み
第5章 「私は未来を見た。うまくいっている未来を」―収奪的制度のもとでの成長
第6章 乖離
第7章 転換点
第8章 領域外―発展の障壁
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みき
52
良書。上巻は国家はなぜ衰退するのかというよりも発展した地域とそうではない地域を比較検証するような感じ。文化や人種ではなく国家の制度が収奪的であるか否かによるという論調は非常に面白く読めた。確かにメキシコとアメリカの国境や韓国と北朝鮮を見ると頷かざるを得ない。さて日本を見ると包括的な制度を採用し比類なき発展をした過去に比べ、今の制度が包括的かというと収奪的な面が目立っているように感じている。ここからの日本がこのまま先進国のままでいられるか重要な局面を迎えていると思うが残念ながら明るい予想はできない。2024/11/25
syota
43
国王や独裁者、少数の特権階級が決定権を握っていると、自己の権力や既得権を守るために現状を変えようとする動きを徹底的に弾圧する。大きな利潤を生む活動(貿易、専売事業など)はすべて自分たちが独占し、新規参入を許さない。その結果経済は停滞し、国の富は時がたつにつれ少数の特権階級に集約され、大多数の国民はどんどん貧困に陥っていく。歴史上大部分の国が衰退した原因はこれだとして、様々な具体例を上げている。産業の持続的発展や衰退に関しては極めて説得力のある理論だ。ただ、これで国家の衰亡を全て説明しようとするのは疑問。→2021/12/06
Nobu A
42
ダロン・アセモグル&ジェイムズ・A・ロビンソン共著(翻訳版)初読。16年刊行。マサチューセッツ工科大学教授とシカゴ大学教授。共に本年度ノーベル経済学賞受賞者。それが本書を購入した理由。論旨は社会制度がどのように形成され、国家の繁栄にどうのように影響してきたか。制度ってある意味動機付けに直接結びつくものでは。そういう意味で影響は甚大。他方、この手の書籍は「ホモ・デウス」「文明崩壊」「銃・病原菌・鉄」等、数年毎に出版されているような。膨大な量のデータと相当の既視感。途中から集中力が切れ、後半流し読み読了。2024/12/27
フジマコ
34
気候的、人種的にも大差がなくしかし豊かな国と貧しい国がある。その違いはなんだろう?この本のテーマである。よく似たテーマの本がJ.ダイアモンドの「銃、病原菌、鉄」だ。ダイアモンドは豊かな地域と貧しい地域の違いを地理説で説明した。宗教風習の違いで説明した学者もいる。この本はそれら何れも否定する。収奪的な政治制度と包括的なそれとの違いが豊かな国と貧しい国を分けると言う。富の配分が一部の権力者を中心に行われる国は貧しい国へ移行し、平等だと豊かな国へ移行するのだと。日本や中国のことを考えてしまう…下巻が楽しみだ。2014/04/07
赤星琢哉
32
これはむちゃくちゃ面白い。そして勉強になる。繁栄する国家と衰退する国家は何が違うのか。繁栄には包括的な政治・経済制度が必要で、国民の財産権を堅持し、投資をするインセンティブを与え、イノヴェーション促進し、創造的破壊を受け入れる体制が必要だ。ということがひたすら、様々な歴史を題材にして説明(証明)している。国家に限らず、会社、運営するサービスなど、人が集まるグループ全てに共通するテーマだと思う。経営者、起業家は必ず読んでもいい本な気がする。下巻も楽しみ。2017/06/19