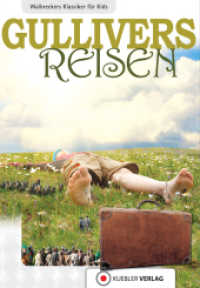内容説明
目を閉じてと言われると口を開く失語症。見えない眼で点滅する光源を指さす盲視。神経心理学の第一人者が脳損傷の不思議な臨床例を通して脳と心のダイナミズムを解説。心とは何かという永遠の問いに迫る不朽の名著。
目次
1 言葉の世界(言葉は「意味野」の裾野をもつ 「語」の成立基盤 語は範疇化機能をもつ 「意味野」の構造 「語」から「文」への意味転換 自動的な言葉と意識的な言葉 言語理解における能動的な心の構え 状況と密着した言葉 言葉はかってに走り出す 過去の言葉が顔を出す 言葉の反響現象 言葉の世界は有機体)
2 知覚の世界(知覚の背景―「注意」ということ 注意の方向性 「見えない」のに「見ている」こと 「かたち」を見ること 「かたち」の意味 二つの形を同時に見ること 「対象を見る」とは何か 視覚イメージの分類過程 対象を掴む 私はどこにいるのか?)
3 記憶の世界(刹那に生きる 短期記憶から長期記憶へ 長期記憶が作られる過程 記憶の意味カテゴリー 記憶と感情の関わり 短期記憶はなぜ必要か)
4 心のかたち(言語と音楽能力は関係あるか 言語と絵画能力は関係あるか 左右大脳半球を分離する 人は複数の心をもつ 心のかたち)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Eee
34
心理学や脳科学に精通していない人にも 読みやすく興味深い本だと思います 科学の発展を目の当たりにしながら 人間の不思議さを知ることができます2017/10/30
kasumi
3
脳に関する話は好物。なぜかな?こんなちっちゃな中に無限の広がりを感じるからかな。…我々は過去の結果であり、過去を背負って生きているが、実際にはその過去をうまく切り離している。自分が任意に思い出すことのできる記憶内容は我々の財産のほんの一部に過ぎない。心は安定かつ不安定、心は選択的かつ恣意的。見た、わかったと思ったことも必ずしも確実ではない。心は状況の中でしか育ちようがないので、状況依存症であるが、一方自己中心性を持っていることも事実。両傾向が交互に作用しつつ心すなわち個性を成熟させていく。…難しい本!2020/11/10
Manari
2
失言の多い(汗)自分は、ちゃんと考えてから話したいが、記載の失語患者では、意識すると言葉がでなくなる・自然と口をつくと滑らかである症例も多い。言葉の自走(暴走と呼びたい)は、連想ゲーム的に話を合わせ作話、を考えると口が滑った言葉は本音だ!と短絡的に言えない可能性もあると。見えてないと訴える患者もテストで見える事もあったり「見える」は視覚だけでは無さそう。言った言わない、見た見てない、で揉めるのも無理ない…。普通/固有名詞、個々の名の区別は意外と頭使ってるようだ。錯視にひっかからない異常、なんだか不思議2026/01/17
カナトキ
2
脳と心の関係について、言語、知覚、記憶、こころ、という各テーマに沿って、著者自身の臨床や過去の脳損傷事例をもとに丁寧に分析しまとめられている。今だからこそ脳機能に対する様々な画像診断も可能になってきたが、当時はまだ正にブラックボックスと言われていた脳について解釈を加えることはかなりの挑戦であったと思う。技術が進歩した現在においても、この姿勢から学ぶものは大きい。2017/11/28
ゆうき
2
脳というハードが損傷を受けた場合、脳が作り出す心というソフトにどのように影響を与えるのか。 脳が損傷を受ければ認識や記憶や行動や感情といった脳が作り出したモノは機能不全を起こす。脳で処理された情報という心も同じように欠損した状態となる。人間は脳があるから様々な情報を認識し処理を行う。その結果として心が生まれ自己となる。脳によって心が生み出され、脳の状態によって世界に対する認識も変容する。2014/07/10