内容説明
科学史の第一人者による「学問の歴史」。科学革命で生まれた新たなパラダイムが学問的伝統を形成していく過程を解明する。古代以来の東西学統の比較から、学会誌などのメディアの発明、職業的科学者の誕生、現代のデジタル化まで、社会的現象としての科学と科学者集団を分析。『歴史としての学問』(1974年、中央公論社刊)を学術文庫化にあたって改題し、新たに「学問のデジタル化・グローバル化」を論じた補章を加筆。(講談社学術文庫)
目次
第1章 記録的学問と論争的学問
第2章 パラダイムの形成
第3章 紙・印刷と学問的伝統
第4章 近代科学の成立と雑誌・学会
第5章 専門職業化の世紀
第6章 パラダイムの移植
補章 その後の変革とデジタル化―四十年の時を経て
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
無重力蜜柑
11
四十年以上も昔、クーンのパラダイム論が日本に紹介された直後の本(しかも『科学革命の構造』の訳者)というだけあり、今から読むと歴史的史料の趣。今や見る影もない唯物史観科学論(科学の下部構造決定論)や、ざっくばらんな東西文明比較、体制化された科学に対する批判など、いずれも時代的。とはいえ示唆に富む部分は多々ある。特に科学の本質を科学革命によるパラダイム形成以上にそこで可能となる通常科学にあるとし、それこそが科学と哲学や芸術を分つものというのは個人的には目から鱗という感じ。2022/05/20
Saiid al-Halawi
7
殆んどの研究者は特定のパラダイムを一定に伸張させる通常科学に従事し、残りのごく一部だけが既存の路線から外れた革命科学を唱導する。とはいえどんなに独創のある画期的な理論でもそれを下支えして発展させる支持者集団が後に続かなければパラダイムにはならない。著者がクーン本人よりも忠実だという筋金入りのトマス・クーン主義者を自認。2015/01/25
ぼのまり
6
30年ほど前に出した「歴史としての学問」というタイトルの復刊本。トマス・クーンの「パラダイム論」を中心に科学史について論じている。「パラダイムシフト」に代表されるように言葉だけが本来の意味を見失い、暴走している感があったが、源流はここにあったようです。2013/06/26
クレストン
3
科学哲学の概念「パラダイム」を生んだクーンに学んだ科学史家による科学と社会、組織、規範などの関係性を考察した本。原本は「歴史としての学問」。主に西洋と中国における学問の発展を原理を論じて比較している。また、5章では科学の専門職業化を様々な国を取り上げて論じている。数冊、科学史や科学哲学の入門書は読んでいたが内容は難しく感じた。作者がくみ上げる論理についていくためにはまた別の本などで学ばなければついていけないか。とはいえ学問を特に組織・規範的に詳しく論じた本はないと思うので、手軽に読めることはありがたい。2021/09/26
読書履歴
3
2013年刊。中央公論社『歴史としての学問』(1974)を改題、概説的な補章を付した文庫版。1章〜3章で、古代から科学革命前までの東西学問の性質、パラダイム、印刷メディア等を比較。4、5章は、近代科学の勃興・成立期(17世紀)、成熟期(19世紀〜20世紀)の雑誌、学会、大学等の諸制度の形成から、科学者共同体を解説。18世紀の蒸気機関は伝統職人技術で、科学革命とそれほど接点をもたなかったという話にちょっと驚く。19世紀ドイツの大学制度の影響力も印象的。6章は日本明治期以降の「科学」の受容について。2013/10/04
-

- 電子書籍
- タテの国【タテヨミ】 77 ジャンプコ…
-
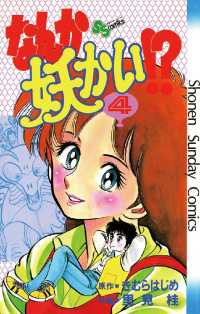
- 電子書籍
- なんか妖かい!?(4) 少年サンデーコ…
-
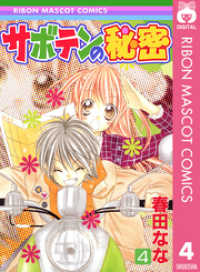
- 電子書籍
- サボテンの秘密 4 りぼんマスコットコ…
-
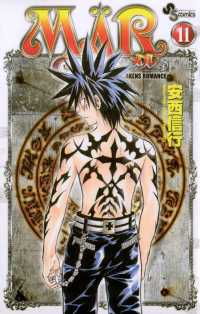
- 電子書籍
- MAR(11) 少年サンデーコミックス





