内容説明
条文を変えても国や社会は変わらない。
「改憲論議」をする前に、必読の一冊!
良い国家や社会を創るために、良い憲法を創ること。それは、すなわち新憲法を制定したり、改憲することではない。憲法の原理を理解した上で、想像力を駆使して我々の「頭の中」に理想のルールを創造することなのである。それはいかに可能なのか。君が代斉唱、一票の格差など、最新の判例に現れた憲法問題を題材に、気鋭の憲法学者が、先端的な憲法学の成果を踏まえながら考察する。これまでにない実践的憲法入門書。
目次
序章 憲法とは何か?
第1章 君が代不起立問題の視点―なぜ式典で国歌を斉唱するのか?
第2章 一人一票だとどんな良いことがあるのか?―クイズミリオネアとアシモフのロボット
第3章 最高裁判所は国民をナメているのか?―裁判員制度合憲の条件
第4章 日本的多神教と政教分離―一年は初詣に始まりクリスマスに終わる
第5章 生存権保障の三つのステップ―憲法25条1項を本気で考える
第6章 公務員の政治的行為の何が悪いのか?―国民のシンライという偏見・差別
終章 憲法9条の創造力
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
そり
17
第三章「最高裁判所は国民をナメているのか?」は、少しばかり過激な題名をつけられたものだなと思った。しかし読んでみると、確かにこれはナメていると捉えてもいいだろう、と思い直した。話は裁判員制度についてのことである。その導入により、被告人は迅速な裁判を受ける権利が侵害され、裁判員に任命された人は望んでもいない勉強をしなければならない。にもかかわらず最高裁は、これが公式の文書なのかと目を疑うぐらい傲慢な論証をしてしまっていた。事情があるのは察せられるけども、最高裁は絶対に聡明ということもないんだなと思った。2015/10/05
RED FOX
13
9条、君が代斉唱、1票の格差、等の問題について賛成、反対の論評をわかりやすく説明。「その時その時の政治的な力関係とか我々の見識の浅さということもあって・・・憲法と言うのは常に未完である。終わりのない仕事なんだ・・・そして世代を越えた終わりのない仕事を僕たちはここまで進めてきた。後に続く君たちも、君達のコンテクストの中で生かしてくれ。」という奥平康弘の言葉の引用で終わる。2016/01/21
RED FOX
12
面白い、読みやすい。今時珍しい護憲な若者・・・って東大からの首都大学准教授ですか、失礼しました(>_<)論破できてるかわからないところもありますが、何せヒューマニズムなところが気持ち良い。佳き本です。2015/05/08
安国寺@灯れ松明の火
11
ある僧侶は、仏教の「諸行無常」「一切皆苦」といった言葉は真理や結論ではなく前提であって、「生が苦で無意味だとしても、どう生きるべきなのか」を問題にしていると言います。憲法が要請する「自衛のための必要最小限の戦力」や「健康で文化的な最低限度の生活」なども、それがどの程度のものであるべきかを常に問題にしているという著者の解説によれば、真理や結論だと思い込んでいることが前提に過ぎない場合があるという点で、相通じるものがある気がしました。興味深い視点を与えてくれる面白い本だと思います。2015/10/19
1.3manen
10
新刊棚より拝借。第5章生存権の検討に注目した。具体的給付を請求する権利(152頁)。生活保護給付は減額という政府の政策であるが、生存権に照らしてどうなのか。公共の福祉の概念もあるが、福祉がシビアに問われる条文憲法25条。評者もCSRのない企業によって健康を奪われたわけで、なにがしかの謝罪が必要なのだが、企業は応じるどころか開き直る始末。本条が尊重される社会であってほしい。木村先生は政府の政策には問題を指摘されているので(180頁)、安心した。9条も戦力は行使してはならない。巻末文献の紹介はお役立ちである。2013/04/29
-
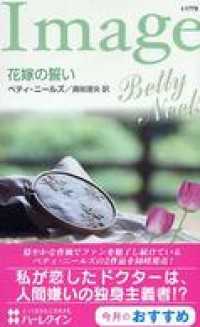
- 電子書籍
- 花嫁の誓い ハーレクイン
-
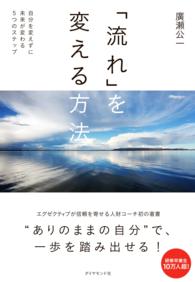
- 電子書籍
- 「流れ」を変える方法







