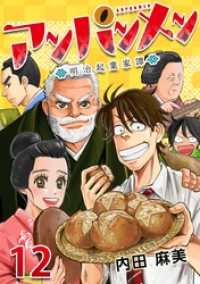- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
「これからがデジタル革命の後半戦。飛躍的に能力を拡大していくコンピュータに人間はますます仕事を奪われる」
MITスローン・スクール、デジタル・ビジネス・センターの研究者2人が2011年に自費出版した本書の原書であるRace Against The Machineの未来予測は、アメリカ国内外で大きな反響を呼んだ。
本書の2人は、技術の進歩が速すぎて起きる雇用喪失説の立場をとる。つまり、コンピュータとの競争に人間が負け始めていることこそ、雇用が回復しない真の原因であると主張する。
目次
第1章 テクノロジーが雇用と経済に与える影響(雇用なき景気回復 仕事はどこへ行ってしまったのか ほか)
第2章 チェス盤の残り半分にさしかかった技術と人間(先行するコンピュータ ムーアの法則とチェス盤の残り半分 ほか)
第3章 創造的破壊―加速するテクノロジー、消えてゆく仕事(生産性の伸び 伸び悩む所得 ほか)
第4章 では、どうすればいいか(相織革新の強化 人的資本への投資 ほか)
第5章 結論―デジタルフロンティア(デジタル革命は何をもたらすか 謝辞)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
66
本書を読むことをおススメしたいひとは、こんな人。 ・若手・中堅のサラリーマン ・就活中の学生さん ・漠然と仕事の将来について考えている人 ・年収が少しずつ減ることについて「Why?」と思っている人 【参考サイト】年収ラボ サラリーマン平均年収の推移 http://nensyu-labo.com/heikin_suii.htm2013/06/18
Miyoshi Hirotaka
57
19世紀は機械と人間が対立した時代。イギリスでは労働者の暴動が起き、アメリカでは蒸気ハンマーと対決したジョン・ヘイリー伝説を生んだ。20世紀にコンピュータが登場し、能力は倍々ペースで増加。チェスの名人にも勝ち、不可能と思われていた市街地での完全自動運転にも成功。このままでは、雇用は創造的な仕事と肉体労働に二極化するかもしれない。ところが、制度革新や組織革新により人的資本と機械を新しい形で組み合わせることができれば、過去の技術革新がそうであったように生産性と生活水準の飛躍的な増大を享受することができる。2014/01/06
きいち
32
コンピュータ技術の進歩によって新たな仕事が生まれるが、その一方で多くの仕事がなくなる。その変化があまりに急激なため、それについていけない人々が技術的失業に陥る…その後広まった将来予測を2011年にいち早く唱えたMITの研究者たちによるレポート。「特にそれまである程度高給を得てきた中間層がやばい」「資本を持ってない人のステップだった中間層がなくなって二極化が進む」…その後の議論の種は、もうこの最初の段階で出てたのだな。それにしても学歴によるアメリカの年収差がすさまじい。そりゃ無理してでも院に進もうとするわ。2018/12/28
小木ハム
27
メタリックな装丁がステキ。2013年に発行されたテクノロジー失業の本。私達が気を付けないといけないのは、できるだけ機械と同じ土俵に立たないこと、自動化されそうな仕事をどうすれば手放せるか考えること。少しずつ無形資産を築くこと。ルール作り、仕組みづくりに精を出すこと。ブルーカラーも長生きする。指数関数的に増大していく技術は、既にチェス盤の半分に差し掛かっているとの事だったが今どの辺りだろう。日本は既に周回遅れというか、何周遅れなのか。未だに多くの中小企業は受発注を手入力で行っている現実。震える。2018/12/21
ふみすむ
25
鉄道と自動車の登場によって馬が大量解雇されたように、今度はコンピュータによって人間が大量に失業するのではないか、という懸念が現代社会には漠然とあるような気がする。本書の主張は、技術の「速すぎる」発展が雇用を奪っているというものだ。歴史的に、新しい技術は短期的には失業を引き起こすが、長期的には新しい産業を興して雇用を創出するはずである。しかし、コンピュータが人間の労働力に置き換わるスピードが速すぎるために、雇用創出が追いつかず、結果的に雇用の総量は減少しており、また雇用の二極化も進行しつつあるという。2015/12/08