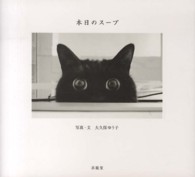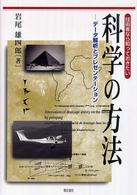内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
いつの時代も、書く行為には剽窃の問題がつきまとう。では剽窃かどうかを判断するオリジナリティの概念は、いつ、いかにして生まれたのか。明治時代に世間を騒がせた剽窃事件を丹念に追いながら、オリジナリティ誕生の過程を跡づける。
目次
1 明治初期~二〇年代(仮名垣魯文剽窃訴訟事件 模倣と剽窃の間 明治一〇年代の無断転載 饗庭篁村と内田魯庵)
2 明治二〇年代(博文堂と偽版 東海散士『佳人之奇遇』偽版訴訟事件 田口卯吉『支那開化小史』偽版訴訟事件)
3 明治三二年前後(模倣と剽窃の区別 翻訳と翻案の区別)
補論 『チーズはどこへ消えた?』盗作訴訟事件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
55
先に読んだ『〈盗作〉の文学史』と異なり、明治のほぼ前半に焦点を当て、江戸期以来の戯作的な執筆姿勢が、作者のオリジナリティが主張され始めて、徐々に現代の著作権の思考に近づくまでを紹介する。補論でいきなり21世紀の事例に飛ぶのだが、明治期の裁判での思考過程が今も続いている点が指摘される。ネットでみんなが意見を掲げられる今、本の世界のあり方も、まるで変わってしまっていることに、果たして著作権の考えは追いつけるだろうか。個人的には、よくある(あった?)二次創作ってのはどうなるのか、すごく気になるのですが。2020/01/13
Kouro-hou
21
明治初頭から三十年程の版権絡みトラブルからみる剽窃事情の本。当時著者は版刷り職人レベルの権利しかなく、費用を一手に受け持つ版元・本屋が談合で元本抄本パクリ本をなあなあでまわしていた。また江戸から続く当時の文化、漢文や戯作は、過去の名文写生、自作抄本愛用で模倣引用当たり前、ジャンル毎の様式美文体など独自性って何?的状況だったのだ。しかし西洋に追いつくべく法体系を整え、著作の概念も浸透し、新旧の価値観の激突が訴訟になって表面化したのだ。今日新の立場から振り返る事が多い問題を、旧の立場からも考える点が興味深い。2015/05/30
kozawa
3
非常に面白く読んだ。主に明治期の文学と著作権に関する話題から明治に急著作権法が成立する頃まで。近代著作権が急激に輸入され日本的文化の中に入っていく。これらのおまけで、その延長線上で良く言われる「明治時代のフリーダムな翻訳文学」がどういう文学・翻訳の環境下で行われたのかなども。さらにおまけでチーズはどこへ行ったか周りのゼロ年代のパロデイ・著作権周りについても明治期のと対比させて眺める。本書の執筆で参考にできなかった未発見の明治期著作権裁判記録が見つかると更に研究が進むのだろうかはてさて。2012/03/12
rbyawa
2
k012、あらぬ方向に面白かったがいささか予期しない方向に疲れた。簡単に言うと「戯作ならこの程度の改変で別の作品と認められる、タイトル被りはご法度」のようなルールを政治小説に当て嵌めて当時の司法にしきりに首を捻っている辺り…いやいやベストセラーに乗っかるのとそうでないのは普通に別物では、となったが、法律にも政治小説にも戯作にも詳しくて良かった。読み終わって気付いたが明治前期の社会においては「パクる側もれっきとした有名人」であり、パクられ側の知名度に一方的に乗っかる存在ではないのか、確かにちょっと違うか…。2020/01/24
ヨシツネ
1
権利意識が明治に輸入されたことで著者の権利が拡大されたというのは、やはり時代に合わせた変化を見る重要性を感じる2018/04/17