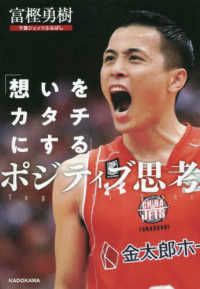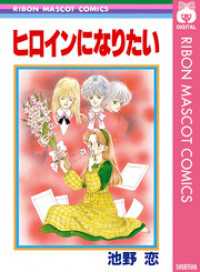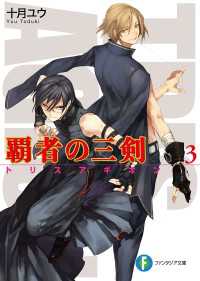内容説明
近代哲学の祖とされ、「心身二元論」に拠ったデカルト。国家契約説をとなえ、「万人の万人に対する戦争」で知られるホッブズ。「神即自然」を主張したスピノザ。十七世紀の哲学シーンを彩る三人の思索は、動乱期のヨーロッパを生きたゆえの魅力にあふれている。神、国家、物体と精神……、根本問題をめぐる三様の思索を、鮮やかに浮き彫りにする。(講談社学術文庫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マウリツィウス
20
【デカルトと近代思想】近現代思想の先駆化された領域をボルヘスが意図導入したことが挙げられるが、そのフィクション性を再吟味、神秘主義体系論とは明らかに異なる点でスピノザは評価すべき。何故なら新約聖書=キリスト教唯一概念保証との照応において表題三者はその存在事実を否定していない。旧約的とされるスピノザでさえも神の肯定と容認は『エティカ』内に見られ、すなわち《神》否定論は無意味かつ不可能という前提から発した主軸を発見する。「近代哲学/思想」断頭台執行者たちへのアンチテーゼこそが本著の意図でもあり、急進性と大別。2013/06/04
YO)))
15
スピノザが『神学政治論』において、(彼以外の全ての人がそうしたように)「真理」と紐付けて聖書を読み解くのではなく、それ(真理)とは無関係に「敬虔な信仰」を成立させる、ある種の言語ゲームの規則・規範を剔出しようとし、それはデカルト左派からすら痛烈に批判された、という話が特に面白かった。またスピノザの語る唯一の実体としての神=自然について、起源も原型も数もない「無数の異なる属性(の差異)の無限の反復」そのものではないか、との議論もとても興味深く読んだ。ドゥルーズなどを踏まえた著者一流の読み解きなのだろう。2024/11/03
karatte
14
再読。ホッブズについて論じた序盤の二論文は、初読時よりずっと興味深く読めた。が、それにしてもスピノザだ。『神学政治論』のクレド・ミニマムの本質を敬虔の言語ゲームとする「スピノザと敬虔の文法」や、聖書の教えを真理から解離させるのも厭わぬ驚異の「スピノザの聖書解釈」は謎解きミステリの如くスリリングだし、ジル・ドゥルーズのお株を奪う差異と反復の超展開を繰り広げる後半の諸論文は、テクスト読解の極北を見るかのよう。2019/04/27
D.Okada
6
ホッブズの契約論の論理構成が破錠せざるをえず、そのことをスピノザの契約説がさらけ出しているということを論証した「残りの者――あるいはホッブズ契約説のパラドックスとスピノザ」や、難解なスピノザの『神学政治論』の直面する課題を「不敬虔」の問題、すなわち「だれが、いかなる権利に基づき、またいかなる権威をより所に、いかなるものを不敬虔として断罪しうるのか」と定式化して読み解いていく「スピノザと敬虔の文法――『神学政治論』の「普遍的信仰の教義」をめぐって」など、学術雑誌に掲載された10の論文を収録。スピノザ読もう。2013/10/25
amanon
4
興味深い記述が少なからずあったとはいえ、やや駆け足で読んだため、理解の程はかなりあやふや。とりあえずスピノザの『神学・政治論』について論じた物はある程度前知識があったので、少なからず示唆を受けたが。最後に収められた文章でも強調されているが、スピノザという思想家が放つ独特な魅力と同時にある種の途方の無さ、わかりにくさを改めて垣間見た気になった。個人的にとっつきにくく思われたのは、冒頭のホッブスについての物。注釈では数列(?)が引用されたりして、余計に混乱させられた。時間があるときにじっくり読み返したい。2014/08/26