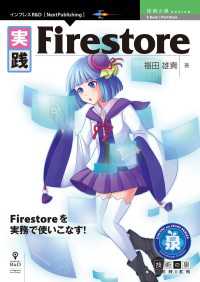- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
尖閣問題、反日デモなど、中国の世論が日本に及ぼす影響がますます大きい。長い中国在住歴を持つ著者は、一般に言われるような知識人の民主化運動よりも、インターネットの普及によってごく普通の人々が「モノ申す権利」=「話語権」を獲得したことが、中国に大変化をもたらしつつあると喝破する。「モノ言う人々」を質・量ともに変貌させるネットの危うさ、メディア管理の限界に立つ体制側、しかし巨大な国で強固な体制なしには生きられない人々自身のジレンマ。西側の思い入れだけでは見えない中国を描く!【目次】はじめに――モノ言う人民の台頭/第一章 中国における“モノ言う権利”/第二章 為政者の「喉と舌」から大衆の代弁者へ/第三章 インターネットにあふれ出した大衆の声/第四章 変質する愛国・反日デモ/第五章 経済の自由化で開いてしまったパンドラの箱/おわりに
目次
はじめに――モノ言う人民の台頭
第一章 中国における“モノ言う権利”
第二章 為政者の「喉と舌」から大衆の代弁者へ
第三章 インターネットにあふれ出した大衆の声
第四章 変質する愛国・反日デモ
第五章 経済の自由化で開いてしまったパンドラの箱
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
wiki
14
昔の本。10年足らずで本書は化石のような情報になってしまった。インターネットが如何に中国の言論を変えたか。その利益と課題について。2011年2月執筆とあってツールがスマホに変わる以前の様相を語る。今の世界はスマホでほぼ全て解決出来るようになった。顔認証もGPSも音声記録も財布も全ておさえることができ、言動パターンや検索履歴、写真などで嗜好や需要、将来何をしそうかまで予測できるAIが開発されている。人間が行っていた検閲もAIに取って代わる。斯様な環境の下でインターネットはどこまで真に開かれた存在であろうか。2020/06/01
KBOSN
1
「中国の若者は中国が好き(愛国心が高い)なのであって、共産党を盲目的に信奉しているわけでは無い」との指摘が鋭い。共産党が愛国精神を損ねる国家運営をした場合には共産党政権の転覆(少なくとも大きな痛手は被る)の可能性もあるのでは。2019/06/14
つんたお
1
いくら経済が発展しても、中国ってのは共産主義だから、厳しい言論統制が行われていて、西側のような言論の自由はないと思っていた。 確かに、依然としてそういう部分はあるのだけど、インターネットメディアの発達とともに、一般庶民にも発言の場が与えられ、それが社会を大きく変えようとしている。 多くの具体例をひいて、中国社会の変容を教えてくれる好著。 2012/11/27
toshokan-no-hito
1
百花斉放百家争鳴、文化大革命という過去を持つ国。「上有政策、則下有対策」というしたたかさを持つ国。「党」の指導がどれほど困難か。激情に駆られて発言する前に、ふと立ち止まって、冷静にかの国を注視する必要を感じさせてくれた。現代社会(どの国であっても)において、情報とは受け取るものではなく、自ら探し選び取るものです。「中国には言論の自由がない」と、一方的に流れてくる情報だけでお嘆きの貴兄にご一読をオススメします。で、日本はホントに自由なの?2011/02/22


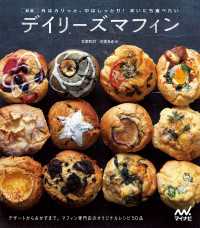
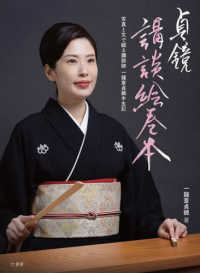
![グラフィック版 ソフィーの世界[分冊] 第21章 「20 世紀」](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1799412.jpg)