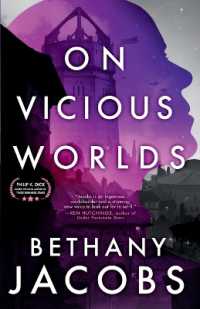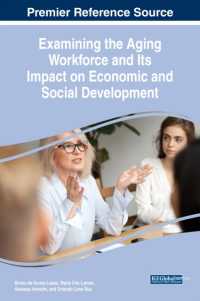- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「目からウロコ」「衝撃的」「出色」と各界から絶賛の嵐!2011年度サントリー学芸賞受賞!(芸術・文学部門)。2011年度国際ポピュラー音楽学会賞(非英語部門)受賞、2011年新書大賞10位。明治・大正期の自由民権運動の中で現れ、昭和初期に衰退した「演歌」。これが60年代後半に別な文脈で復興し、「真正な日本の文化」とみなされるようになった過程と意味を、膨大な資料と具体例をもとに解き明かす。【光文社新書】
目次
はじめに―美空ひばりは「演歌」歌手なのか?<br/>第1部 レコード歌謡の歴史と明治・大正期の「演歌」(近代日本大衆音楽史を三つに分ける 明治・大正期の「演歌」 ほか)<br/>第2部 「演歌」には、様々な要素が流れ込んでいる(「演歌」イコール「日本調」ではない 昭和三〇年代の「流し」と「艶歌」 ほか)<br/>第3部 「演歌」の誕生(対抗文化としてのレコード歌謡 五木寛之による「艶歌」の観念化 ほか)<br/>第4部 「演歌」から「昭和歌謡」へ(一九七〇年代以降の「演歌」 「演歌」から「昭和歌謡」へ ほか)