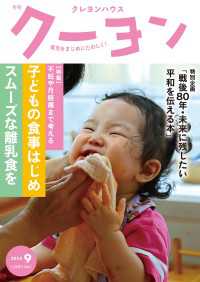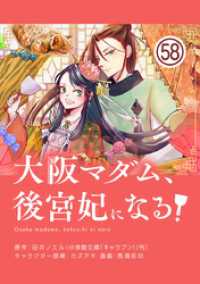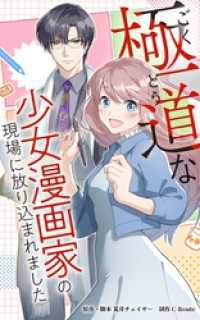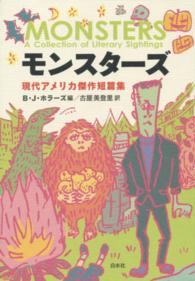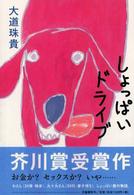内容説明
1987(昭和62)年、国鉄の分割・民営化によって誕生したJR東日本は、1万両を超す車両を保有する日本最大の鉄道会社となる。しかし発足した当初は、国鉄時代の古いタイプの車両が大半を占め、技術革新の遅れも目立っていた。民間会社に移行し、顧客優先の志向のなかで、どのようにしてJR東日本独自の車両が生み出されていったのか。その過程と舞台裏を、JR東日本で運輸車両部長などを歴任し、運転計画や車両開発に深く関わってきた、白川保友氏の証言によって浮き彫りにする。
■著者紹介
白川保友(しらかわやすとも)
1971年、国鉄入社。長野運転所助役(381系担当)、勝田電車区長、蒲田電車区長、運転局車務課補佐(電車検修)、東京南鉄道管理局電車課長など、主として電車関係の仕事に従事。1987年、東日本旅客鉄道入社。広報課長、東京地域本社運輸車両部長、取締役鉄道事業本部運輸車両部長、常務取締役鉄道事業本部副本部長などを歴任。2004年よりセントラル警備保障(株)。社長、会長を経て現在は取締役相談役。
和田 洋(わだ ひろし)
1950年生まれ。神奈川県藤沢市で東海道本線の優等列車を見ながら育つ。1974年、東京大学文学部卒。新聞社勤務を経て現在は会社役員。子どもの頃から鉄道車両、とくに客車を愛好し、鉄道友の会客車気動車研究会会員。著書に『「阿房列車」の時代と鉄道』(交通新聞社・2015年鉄道友の会 島秀雄記念優秀著作賞)、『客車の迷宮』(交通新聞社新書)などがある。
目次
●目次
序 章 国鉄改革からJR発足へ
第1章 209系から始まる通勤・近郊電車の革新
第2章 通勤・近郊電車の標準車となったE231系
第3章 線区のニーズに合わせた特急電車のバラエティ
第4章 新幹線の高速化・多様化の歩み
第5章 E5系・E6系新幹線による高速化への再挑戦
第6章 国鉄型から脱却した気動車の開発と進化
第7章 最後の寝台特急「カシオペア」の誕生
終 章 劇的に変わった車両メンテナンス
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
竜玄葉潤
のげぞう
やまほら