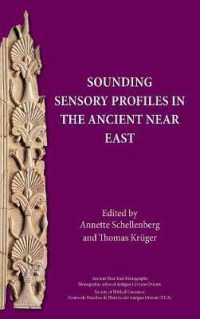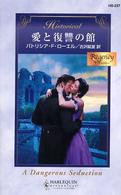- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
中世において、朝廷・幕府以上の存在感を持っていた寺社=境内都市=無縁所。そこには、「世を仕損なった」人たちが、移民となって流れ込んできた。なぜ人は、有縁の世から逃れ、無縁世界で一時の命を繋ぎ再起を賭けようとしたのか。また、無縁世界が有縁世界に対抗しえたのは、どんな思想、どんな実力によるものなのか。網野善彦や民俗学の知見を批判的に乗り越えつつ、たしかな史料で日本中世を描く。
目次
序章 秀吉のバイプレーヤー―木食応其と無償の善意
第1章 山門摩滅か武家滅亡か
第2章 無縁所の魅力
第3章 なぜ人々は駆込むのか―未開国家と無縁所
第4章 これが無縁所だ!
終章 無縁所と中世社会―時代へのメッセージ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
moonanddai
6
網野氏の「無縁所…」を読み、無縁所の自由・平和・平等という、何となくソフトなユートピア的なイメージがストンと落ちなかったのですが、その外にある苛烈な「検断(犯罪捜査)」「徴税」といった弱肉強食の有縁の社会があったからこそ庶民は「無縁」の社会に駆け込んだといわれれば、わかるような気がします。そこは人生をやり直せる場、いわば慈善施設であり再生工場というべきもので、それは何となく世間に認められるものというより、認めさせることができる「力」、武力であり呪術、文化力、経済力を持つ寺社だからこそということのようです。2022/10/14
4610tosan
3
これは大変面白く読ませていただきました。なかなか中世の大寺院や商工業、芸能などは、貴族や武士の付け足しみたいな説明しか読んでいなかったので、なぜあの時期に仏教寺院が大きかったのか、商工業はどうやって発達したのか、目からうろこでした。国土や生産者から富を絞り上げる古代国家と貴族、その仕組みを暴力で運用した武士、それ以外の政治力があって中世社会が成立してかつ進化(!)していったという説明は、私にはとても説得力がありました。2017/11/27
米村こなん
3
中世日本社会における寺社勢力の権勢の凄まじさが伝わる良書。高校日本史の副読本にしたい。2016/03/27
おらひらお
3
2010年初版。文章の書き方かもしれませんが、難しい内容をわかりやすく書いてある本です。それに加えて新知見も多く、購入すべき本といえます。ただ、著者の写真は面白いのですが、前作と変えてもらえるともっと面白かったと思います。2012/10/04
HANA
3
中世の歴史を寺社側からまとめた一冊。寺社がアジールであったとはよく言われるが、ここではその働きと限界までがわかりやすく説かれている。隆慶一郎の小説とか読むと、無縁所がもっと素晴らしいもののように思えるのだが。現実はこんなものかなあ。2010/05/30
-
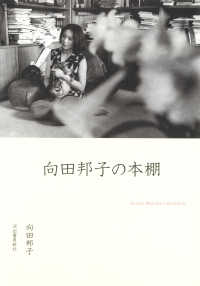
- 和書
- 向田邦子の本棚
-

- 電子書籍
- 嘘だらけの日仏近現代史 SPA!BOO…