- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「いったいこの薬、何からできているのだろう?」高血圧薬、糖尿病薬、高脂血症薬……日頃飲んでいながら、その薬の中身を知っている人はほとんどいない。日々開発が進む薬品の世界――科学者たちの苦闘と、ちょっと意外な「薬」誕生の物語。謎に満ちた創薬の世界を紹介する好ガイド!
目次
高血圧の薬
リウマチや救命の薬
糖尿病の薬
高脂血症の薬
胃薬
花粉症の薬
心筋梗塞や脳梗塞の薬
細菌感染治療薬
抗ガン剤
ウイルス感染症治療薬
うつ病、片頭痛、パーキンソン病、アルツハイマー病の薬
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fukafkacraft
3
ペニシリンが青カビから単離されたことは誰でも知っているが、抗生物質が放線菌から採集され、どういう分離プロセスを経て精製されるのか等を大雑把に知りたかったのだが。あるいは、有名な薬の成分が何から出来ていて、どうやって精製したのか、有効成分が何%含まれているのか等を知りたかったのだが、ごく一部しか書かれていない。創薬に関する雑学として実際に企業名をあげて大雑把に精製経緯が説明されている点は良い。無駄に専門的な記述も散見している。あとはドラッグラグの問題提起を少々。日本での分子標的治療の遅れは洒落にならない。2018/01/25
もき
1
題名は胡散臭い健康啓蒙書のようですが、中身は科学的示唆に富んでおり面白い本です。今年読んだ新書の中では最高の部類に入ります。症状別に創薬の近現代史が章だてられ、現在使われているメジャーな医薬品の発見された経緯、第1世代新薬の抱える問題と解決、そして企業間の開発競争などが簡潔にまとめられています。創薬科学入門として良質な書ですし、薬理学的観点からも切りこまれているので薬剤師志望の薬学部の学生さんの理解にも役立つかも。全ての医薬品に構造式が付されてあれば更によかったな、と思うので余白に構造式を書く予定。2011/08/27
ヤマセミ
0
蛇毒から高血圧の薬、トカゲの毒から糖尿病の薬とか、どうやって薬の開発がされてきたのかというハラハラするような物語など、難しげに思えた薬学が面白く読めた。今までわけわからなかった、薬の専門用語がそうだったのかと納得することも多々。何も知らずに薬を飲んでたなあと思いました。日本は認可されてる薬がとても少なくて残念な状況にあることとか、早くなんとかならないものでしょうかねえ。2015/03/04
ビリー
0
タイトル的には医薬業界に対する警鐘っぽい印象(出版社の意図だろうか?)だけど、内容は医薬品の研究開発への賛歌だった。専門書ではないが一般向けとしてはやや小難しいし感じで、対象としている層がいまいちハッキリしない。薬学生あたりに読んでもらうべきだろうか。薬の原料として植物や菌類は結構出てくるので僕はそこそこ楽しめた。2013/06/08
uburoi
0
創薬という言葉が頻出する。樹や草から、動物や虫から、化学物質や鉱物から、さらに細胞からも薬は創られる。中山教授のiPS細胞だってちゃんと登場するから驚きだ。薬を造る過程は実に劇的だ。まさに劇薬だ。薬なしに医師の治療が存在しないことを『梅ちゃん先生』が再認識させてくれたが、それにしても次々に病を克服する創薬の力はSF的でもある。後ろにあったトレハロースが実現したら『2001年宇宙の旅』の睡眠旅行も現実になるかもしれない。それが2101年だとしても。2012/10/20
-

- 電子書籍
- 待宵は褪せぬ面影と(5) COMICエ…
-

- 電子書籍
- マッチングアプリなんて信じません!【タ…
-
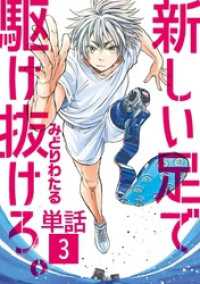
- 電子書籍
- 新しい足で駆け抜けろ。【単話】(3) …
-
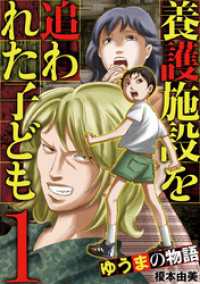
- 電子書籍
- 養護施設を追われた子ども~ゆうまの物語…





