- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
ある日「永劫回帰」の思想がニーチェを襲う。この着想をもとに一気呵成に書き上げられた『ツァラトゥストラはこう語った』は、二〇世紀の文学者・哲学者の多くを惹きつけ、現代思想に大きな影響を与えた。文学の伝統的手法を駆使しつつも、ときにそれを逆手にとり、文体の実験までも行うニーチェ。一見、用意周到な筋立てや人物造形とは無縁と思われるこの物語は何を目論んでいるのか。稀代の奇書に迫る。
目次
第1部 ニーチェのスタイル(世界を読み解く技法
舞踏する精神)
第2部 『ツァラトゥストラはこう語った』を読む(思想とパロディ-序説
賢者からソフィストへ-第一部
分身たち-第二部
ツァラトゥストラの帰郷-第三部
高等な人間たち-第四部)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bibliophage
6
久しぶりにニーチェ関連本を読んだが、面白かった。ニーチェ作品は手紙なども全て含めて考察しなければならない、分野としては''メニッペア''、パロディー、唯一の真理ではなくニーチェは多元性を主張、ツァラトゥストラ=ゾロアスター、二元論、パラドクス、ヘーゲルの弁証法は収斂だがニーチェは外へ、ツァラトゥストラの綱渡り師と道化、第4部の存在など理解する上でのヒントがたくさん出てきた。文献学を専攻していただけあり、ニーチェの知識量は半端じゃないなと。あと、キリスト教の教養がないと理解が難しい部分も多いと思った。2016/02/07
♨️
5
文学史・美術史に依拠しつつ一章一章の位置付け、一つ一つのモチーフの解釈をしながら、そのネットワークから『ツァラトゥストラ』というテクストを立体的な仕方で読んでいこうとしている。現代思想の源流としてのニーチェという見方も意識しつつ、のちに様々な哲学者が生み出す概念の種があるのではないかということも意識的に書かれていて(やや力技のように感じることもあるけど)刺激的な解説書だと思う。ツァラトゥストラを読むときに脇に置いておくって使いかたが一番良さそう。第四部や「三段の変化」「舞踏の歌」あたりが読みたくなった。2020/07/09
いいほんさがそ@蔵書の再整理中【0.00%完了】
5
**注)哲学入門書・ネタバレ**ニーチェと哲学系SFの読解の為読了。ゼノサーガというTVゲームを興じておりますが、ゲームに盛り込まれた『発狂直前のニーチェが到達した"永劫回帰"の発現に到るプロセス』を追う上で非常に本書が役立ちました。しかし、哲学そのものについては、本書は"何の役にも立たない事"を教えてくれます。あたかもニーチェが発狂して最期を迎えたように、思想世界の泥沼にはまり込む感覚を抱きながら本を閉じることになる。これこそが超人への道だと示す様に・・・。ニーチェをさらに読み進めたい方にお勧めします2012/03/04
大森黃馨
4
先日読了したニーチェ&ツァラトゥストラ関連の書とはまた随分と違う事に戸惑うニーチェ&ツァラトゥストラそれを本当の意味で理解し己の血肉とするのにはそれこそ文字通りの意味で己の魂や全生涯寸分の時間すら全てをニーチェに贄として捧げる必要がありさもなくば扉は微かにすら開かれぬそれすら始まりに過ぎないのではないかと思う 2023/01/17
karatte
4
ニーチェ自身すらその位置づけを決定しておらず、長らく蛇足と思われていた第四部が、実は既存の三部作を笑劇に変換するためのものであったとする見方にはいたく感心した。2009/10/15
-
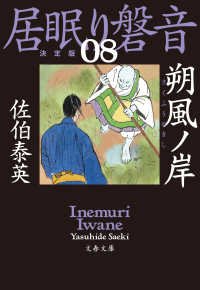
- 電子書籍
- 朔風ノ岸 居眠り磐音(八)決定版 文春…
-
![[図解] 人をその気にさせる悪魔の心理会話](../images/goods/ar2/web/eimgdata/9987299520.jpg)
- 電子書籍
- [図解] 人をその気にさせる悪魔の心理…







