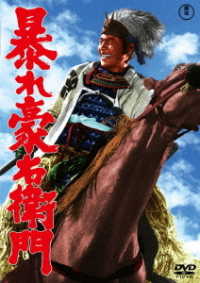出版社内容情報
小学校で男の子を伸ばすには? 15000人の子どもからわかったこと◎小学校で勉強もスポーツも「伸びる男の子」にするには?
こんにちは。竹内エリカです。わたしは20年にわたって子どもの心理や教育を研究してきました。子どもの成長には、何が必要なのか? これまでに指導した1万5000人の子どもたちを見る中で、わかってきたことがあります。
まず、男の子と女の子は特性が違います。お母さんの考え方を押しつけすぎると、男の子は元気にたくましく育ちません。「ダメ!」と言いすぎず、ある程度やりたいことをやらせるほうがいい。男の子の特性を知り、長所を伸ばしましょう。
そして、6歳を過ぎるといよいよ小学校に入学となります。学習、運動について親御さんもその力を伸ばしてあげたいと思うことでしょう。
こどもにはその年齢によって成長する力があります。7歳の頃は運動する力が伸びますし、8歳の頃は勉強する力が伸びます。赤ちゃんを生んだときの気持ちに戻って、0歳に戻ったつもりで、小学生のそれぞれの年齢で、生きるのに必要な力を伸ばしていきましょう。
この本では、男の子の特性を生かし、さらに小学校の6年間に、勉強とスポーツの力を伸ばして、豊かなお友だち関係を築けるよう、具体的な方法をたくさんまとめています。ぜひ、読み進めてみてください。
◎イントロダクション
小学校で勉強もスポーツも 「伸びる男の子」にするには?
「勉強しなさい」よりも、「早寝早起きしよう」。まず、よい生活習慣を身につけさせよう
男の子には、勉強では「小さな達成感」をたくさん味わわせてあげるといい 他
◎6歳の章 小学校への入学前に、「好奇心」を育てる
男の子が苦手な「落ち着き」はトレーニングで身に着けさせられる
「学校って楽しい場所!」母親の明るい言葉がけで、小学校に行きたくなる
「絶対に、できるよ」と言ってあげると、本当にできるようになる
6歳の「勉強」「運動」「お友だち関係」 他
◎7歳の章 小学1年生は、「運動能力」を伸ばす
小学校入学は、「生活習慣」をしっかり身につけるチャンス
「物の地図」をつくって置き場所を教えれば、片づけ上手になれる
お友だちを家に招いて、遊んでいるのを見れば、わが子の内面もわかる
7歳の「勉強」「運動」「お友だち関係」 他
◎8歳の章 2年生は、勉強の習慣をつけて「学力」を高める
「9歳の壁」を乗り越えるには、自分で学ぶ力をつけさせよう
楽しく勉強できるよう学べる環境をつくり、勉強の習慣をつけるのが親の責任
8歳の「勉強」「運動」「お友だち関係」 他
◎9歳の章 3年生は、社会へ出て行く「自立心」が強くなる
失敗を乗り越えるには、「RQR」の質問で、自分で答えを出せるように導こう
尊敬できる大人、信頼できる友だちが学校の外にもいれば、トラブルに強くなる
9歳の「勉強」「運動」「お友だち関係」 他
◎10歳の章 4年生は、親子で向き合って「継続力」をつける
ギャング・エイジには、「親の正論」ではなく、本音を話せば伝わる
無理なお願いをしてきたときには、「説得してごらん」の一言が効果的
10歳の「勉強」「運動」「お友だち関係」
◎11歳の章 5年生は、反抗しながらも「思いやり」を学ぶ
反抗のエネルギーがいっぱいなとき。「暴言」「暴力」に手出し口出しは無用
わが子を「いじめられる子」「いじめっ子」のどちらにもしない
11歳の「勉強」「運動」「お友だち関係」
◎12歳の章 6年生は、親からの愛情を受けて「自信」がつく
学校でのトラブルでは子どもの言い分を信じ、もし迷惑をかけたなら、一緒に謝りに行こう
スキンシップで自己肯定感が高まる。「7秒抱きしめ」などたくさん触れ合おう
12歳の「勉強」「運動」「お友だち関係」 他
竹内エリカ[タケウチエリカ]
著・文・その他
内容説明
「短い言葉」で叱る。やってほしいことを3回繰り返す…小学校で伸びる男の子にする習慣づけ。男の子の特性を生かし、6年間に、勉強とスポーツの力を伸ばして、豊かな友だち関係を築ける具体的な方法。
目次
6歳の章 小学校への入学前に、「好奇心」を育てる
7歳の章 1年生は、自由に遊んで「運動能力」を伸ばす
8歳の章 2年生は、勉強の習慣をつけて「学力」を高める
9歳の章 3年生は、社会へ出て行く「自立心」が強くなる
10歳の章 4年生は、親子で向き合って「継続力」をつける
11歳の章 5年生は、反抗しながらも「思いやり」を学ぶ
12歳の章 6年生は、親からの愛情を受けて「自信」がつく
著者等紹介
竹内エリカ[タケウチエリカ]
幼児教育者。一般財団法人日本キッズコーチング協会理事長。2児の母。お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課程修了。20年にわたって子どもの心理、教育、育成について研究し、発達支援では多動症・不登校の克服、運動指導では全国規模の大会で第1位他、14賞受賞のコーチ実績がある。「あそび学」を専門にし、あそびによる発達診断、プレイセラピー、運動支援プログラムの研究開発・執筆を行う。その成果を海外の教育国際会議で研究発表している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鈴
seacalf
レモン
shk
おっち
-
![BRUTUS(ブルータス) 2025年 3月1日号 No.1025 [センスがいい仕事って?]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2040545.jpg)
- 電子書籍
- BRUTUS(ブルータス) 2025年…
-
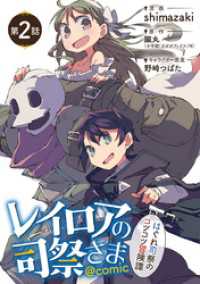
- 電子書籍
- レイロアの司祭さま~はぐれ司祭のコツコ…