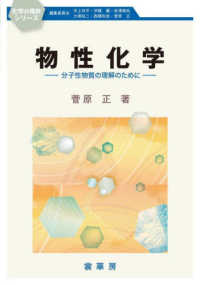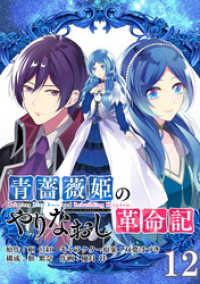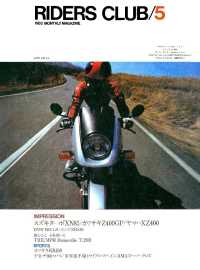- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
膨大なインタビューに基づくケーススタディを通して「パラダイム破壊型イノベーション」という新しい概念を提示する。『イノベーションのジレンマ』に挑む意欲的な一冊。
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、予めご了承ください。試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの端末での表示をご確認ください。
目次
第1章 「戦後日本」とは何だったか(チャレンジ精神の喪失=戦後日本の第一の病理 縮む社会に右往左往=戦後日本の第二の病理 ほか)
第2章 イノベーションの構造(クリステンセンの議論とその誤謬 パラダイム破壊型イノベーション ほか)
第3章 ケース・スタディ「トランジスタ」(トランジスタ 電界効果トランジスタ(MOSFET) ほか)
第4章 ケース・スタディ「青色発光デバイス」(パラダイム破壊 セレンディピティ ほか)
第5章 未来をいかにして創るか(「パラダイム破壊型イノベーション」を生む組織の成功条件 イノベーション・システムの崩壊プロセス ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おだんご@切実
1
パラダイム破壊型のイノベーションを軸にした社会構造について提言し、青色発光ダイオードやトランジスター等の実現を例に解説しているのが面白かった。知の創造と知の具現化の二次元軸を用いて発明のダイヤグラムを明示し、既存理論のパラダイム破壊が必要だと示している。さらに著者は暗黙知の共有不足がパラダイム破壊の障害になっていると述べ、それを解決するには共鳴場を起こすネットワークが不可欠だとしている。共鳴場を起こすための多様性が欠如し、リスクを恐れ研究を萎縮させてしまっているという日本の現状について考えさせられる本。2011/05/08
nchiba
1
図書館で一度借りて読みきれずもう一度借りて読了。形式知と暗黙知のスパイラルと共鳴場によってパラダイム破壊型イノベーションが起きるのか。逆か。パラダイム破壊型イノベーションが起きるためには形式知と暗黙知のスパイラルと共鳴場が必要ってことか。やっぱり「場」がポイントってことかな。もう少し考えてみたい。2011/04/03
おもしろきこともなき世に
0
イノベーションには共鳴が必要であることを説くが、共鳴の場って果たしてデザインできるものかどうか。結果を分析することと、予め目指すこととは、大きな違いがあるのではないかなぁ。2013/12/12
Barrus
0
イノベータたる研究者と経営者の間に筆舌につくしがたい共鳴があってこそ、イノベーションは実現すると筆者はいう。なるほど確かにと思う一方で、いよいよイノベーティブな組織を作り、維持するという課題は、スキルで解決できないのではという思いも頭をもたげてくる。優秀なMBA取得者と資本市場の存在が、イノベーションを途絶させる、というのは、むろん拙速な答えなのだろうけれど-。2012/05/23
noritsugu
0
肝心の部分が分かっていないかも~。クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」にケチをつけている部分も「イノベーションのジレンマ」自体ちゃんと理解できていないせいもあり、正しいかの判定ができなかった。もしかして、色々書かれているが、「共鳴場」さえ認識しておけば OK?2009/11/06