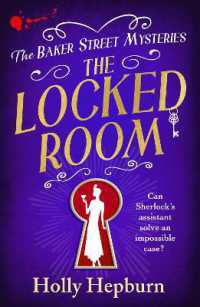- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
ショーペンハウアーの魅力は、ドイツ神秘主義と18世紀啓蒙思想という相反する二要素を一身に合流させていたその矛盾と二重性にある。いまその哲学を再評価する時節を迎えつつある。
目次
第1巻 表象としての世界の第一考察―根拠の原理に従う表象、すなわち経験と科学との客観(世界はわたしの表象である。 主観と客観は直かに境界を接している。 根拠の原理の一形態としての時間。世界は夢に似て、マーヤーの面紗に蔽われている。 物質とは働きであり、因果性である。直観能力としての悟性。 ほか)
第2巻 意志としての世界の第一考察―すなわち意志の客観化(事物の本質には外から近づくことはできない。すなわち原因論的な説明の及びうる範囲。 身体と意志とは一体であり、意志の認識はどこまでも身体を媒介として行なわれる。 身体は他のあらゆる客観と違って、表象でありかつ意志でもあるとして二重に意識されている。 人間や動物の身体は意志の現象であり、身体の活動は意志の働きに対応している。それゆえ身体の諸器官は欲望や性格に対応している。 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イプシロン
44
哲学とは思想の自殺である。またそこからの再生である。そのような覚悟をもって読むべき書が『意志と表象としての世界』である。導入部はいささか古典的な哲学とは違っている。「我思うゆえに我あり」という主観(観念論)的立場にたっているのではない。かといって「実存は本質に先立つ」といった客観(実存主義)的立場にたっているのでもない。ショーペンハウアーは、表象という事象とは何かという、一種の現象学的視点をもって哲学的自殺を試みる。したがって、導入部から引き出されるのは、表象は見るものと見られるものの関係(主観と客観)2020/10/22
かわうそ
37
『いやしくもこの世界に属しているもの、また属することができるものはことごとく、主観による以上のような制約をいやでも背負わされているのであって、世界に属するすべてものはただ主観に対して存在するにすぎない。世界は表象である。このような真理はなにも特別目新しいとはいえない。すでにデカルトが出版点となしていた懐疑的な考えのなかにもこれはあった。』P7 デカルト以前は客観にこそが真理あると考えられていました。デカルト以後は主観にこそ真理があるとされそれが近代の個人主義を支える思想となったのです。2023/09/03
かわうそ
36
概念は表象の表象である。概念は厳密には直観を表現しきれないなのであって、概念はすなわち抽象的でしかない。つまりは理性も抽象的であって、抽象的であるということはそれぞれの人間によってどこが拡大されるか縮小されるかは変わる。 また、今までの哲学は主観と客観を因果性で結びつけていたと彼は言う。しかし、主観と客観を因果性で思考することは不可能であって、それは主観から出発したとしても客観から出発したとしても同じである。結局は客観それ自体を認識できるという誤謬が含まれることになり、世界は表象であるということを見落とす2023/12/08
かわうそ
32
『世界に属するすべてのものはただ主観に対して存在するにすぎない。世界は表象である。』P7 『したがってこれら(時間とか空間とか因果性とかいう)諸形式の各々は、表象なかの特殊な一部門とみなされるにすぎないであろう。』P6 彼が言いたかったことはつまり、世界のすべてのもの、全ての形式は各人の表象に従属するということです。この点から、彼の哲学は現象学の考え方にもつながっていくのでしょう。『普通の人間と類人猿との差は、ショーペンハウアーと普通の人間の差よりは小さい』という言葉にも納得せざるを得ない本です。2022/12/06
加納恭史
20
ショーペンハウアーは1788年ハンザ同盟の都市ダンツィヒに父フローリスの長男として生まれた。父は銀行業務なども手掛ける裕福な商人で、母ヨハナは名門トゥロジーナ家の娘。彼女は小説家で旅行記も執筆。父は息子を立派な商人にしたい。商人になることを約束し、父は息子をオランダ、フランスなど二年に渡る世界旅行へ伴う。その後息子は豪商イェニシュのもとで実務を習う。1805年、父は急逝し、母ヨハナは夫の商会をたたむ。1807年ショーペンハウアーはイェニッシュ商会を辞め、父の遺産を相続し、ゲッティンゲン大学に入学する。2023/11/14
-

- 電子書籍
- 恋フレ ~恋人未満がちょうどいい~ 2…
-
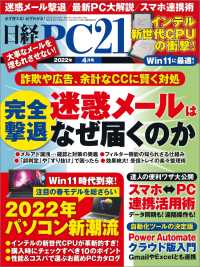
- 電子書籍
- 日経PC21(ピーシーニジュウイチ) …