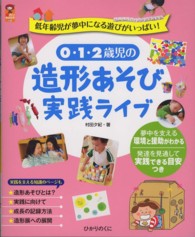目次
1 子どもの自信を引き出すために(「教育の成功」とは?;成長の原動力;挑戦する子ども、しない子ども ほか)
2 子どもの自信を引き出すほめ方(子どもの自信を奪うほめ方;大人の都合優先ではなく子どもの幸せを見据えて;結果よりも努力、姿勢、過程 ほか)
3 子どもの自信を引き出す叱り方(叱ることは必要なのか?;価値観をつくる;心の回復力を育てる ほか)
著者等紹介
赤坂真二[アカサカシンジ]
上越教育大学教育実践高度化専攻(教職大学院)准教授。学校心理士。1965年新潟県生まれ。2003年上越教育大学大学院修士課程修了。19年間の小学校勤務を経て、2008年4月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
mori
4
新年度にあたり再読。今年はクラスのあの子に叱らずスタート。失敗を責められ、固まっていた過去を知っているから。「ほめると叱るがセットになって価値観が形成」「叱ることは、他者を適切な方向に導く利他行為」とあり、叱らずいた今週を振り返る。まずは関係づくりと考えスタートしたが不足かなあ…。温かさをベースにした厳しさとでも自信を無くしている子にはやはり温かさと温かさか。いずれにしてもなぜほめるか、叱るか。それは子どもの幸せにつながることかで判断したい。「幸せ」のところは今回初めて腑に落ちた。2019/04/13
mori
2
叱るを考えたくて読む。今回、ドキッとした箇所。「世話を焼きすぎると、子どもの挑戦する意欲は減退し、できることもできるようになりません」「日常の指導場面でいきなり評価されることには違和感を伴う」私は相手の存在を認めているかと振り返る。叱るのところでは、自分の基準について再考する。また、「禁止は相手の主体的な考えや行動を引き出すことにはつながりにくい」に考えさせられた。2017/08/02
gongon
1
「ほめることと叱ることに関する哲学をもつ」という観点で読んだ。①何のためにほめるのか。子どもにとって、良い人生を送るために適したことだからほめる。良い人生とは、自分の中では、自身の幸せに対して主体的になることだと考えている。②叱る基準。人権侵害行為、周囲に迷惑をかける行為、命に関わること。③伝え方。相手の存在を認めた上で伝える。愛を伝える。努力、姿勢、過程に注目。子供を思う姿勢があって、初めて伝わると感じた。子供を思うためには、自分の中に寄り所となる哲学が必要。更新していく。2015/12/01
草食系教師
0
私の尊敬する先生が送別会のときに言ったセリフです。「私のモットーは見返りを求めないことです。」その先生は本当に謙虚な方で、なるほど先生らしいと思って感心しました。この本を読んでその意味がより深く理解できるようになりました。一見当たり前のことが書いてあるようですが本当に大切なことです。叱ることを振り返るいい機会になりました。2014/03/26
-

- 和書
- 課長の会話術



![毎年出る!センバツ40題 理系数学上位レベル[数学1・A・2・B・3]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40103/4010348666.jpg)